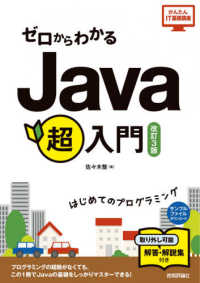内容説明
18世紀終わりに生を享けた伝説の男ラロン・フォキル。彼が作った千以上の“バウルの歌”は、譜面に遺されることなく、脈々と口頭伝承され、今日もベンガル地方のどこかで誰かが口ずさむ。教えが暗号のように隠された詩は、何のために、数百年もの間、彼の地で歌い継がれているのか。アジア最貧国バングラデシュに飛び込み、追いかけた12日間の濃密な旅の記録。
目次
第1章 はじまりの糸
第2章 バラバラの船と映画監督
第3章 聖地行きの列車
第4章 二人のグル
第5章 タゴールとラロン、自由への闘争
第6章 メラという静かな狂乱
第7章 「知らない鳥」の秘密
最終章 ガンジスの祭宴
著者等紹介
川内有緒[カワウチアリオ]
日本大学藝術学部卒、ジョージタウン大学にて修士号を取得。コンサルティング会社やシンクタンクに勤務し、中南米地域の研究を行う。その合間に少数民族や辺境の地を訪ねた旅の記録を雑誌に発表。2004年に渡仏し、パリの国際機関に勤務した後、フリーランスに(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ドナルド@灯れ松明の火
30
平松洋子さんの「本の花」で知った本だが、これが素晴らしかった。読み始めてすぐギュッと心が掴まれる。有緒さんの行動力とその”引きの強さ”には感心する。読む者でさえ一緒にバウルを探していく気になってしまう。思いが強いと、こうも2週間でキーとなる人たちに巡り会うるんだなぁと感じた。名紀行である。 お薦め2020/04/15
tom
28
バングラデシュにバウルという歌う人たちがいる。たまたまそのことを知り、聞いてみたいと思い立つ。情報はほとんどない。伝手を頼み情報を集めたけれど、手探り状態でバングラデシュに降り立つ。日程は行き帰りの飛行機を含めて二週間。到着後は走り回る。そして、通訳の善意やら運の良さなどでバウルの歌を聞き、グルから話も聞けた。小乗仏教的な哲学の世界らしいけど、宗教でもないらしい。バウルとは「風を探す」という意味の古語。風とは呼吸のこと。バウルは命の風を探す人のこと。ネットでバウルの歌を聞いてみた。とても魅力的でした。2022/08/13
hit4papa
16
"パウルの歌"とは哲学。教えを巧みに隠しながら、伝承するための手段。数百年も受け継がれる自分探しの旅の歌。なんとロマンチックなのでしょう。著者は、”バウルの歌”を聴きに、バックパッカーも立ち寄らないという国バングラディッシュへ旅立ちます。著者の情熱は、読者に代わって、知らない世界の扉を開いてくれるでしょう。
パンダ女
13
最近写真付きの<完全版>が出版されたらしくそのツイートで本書の存在を知り図書館で借りた。川内さんの本は二冊目だが、今のところ100%泣かしてくる。別に暗いテーマじゃないのに。言葉が優しいんだよなぁ。バングラデシュってよく知らない国だったけど、人はとても良さそう。貧しい国なのに幸せそう。バウルには結構あっさりと会えたし、そもそも定義が曖昧みたい。人類のグレートジャーニー、我々が行ってきた蛮行の歴史、人類をより良くするには自分たちより優れた選りすぐりの子孫を残す必要がある、ってのが印象的。完全版買うかも!2020/07/17
ふぇるけん
12
バウルとはバングラディシュの無形文化遺産の伝統芸能である。元国連職員の著者がひょんなことからバウルに興味を抱き、現地まで訪ねて体験した旅行記。もっとも貧しい国という不名誉なレッテルを貼られている国だが、この著書からは人々の温かなやさしさが伝わってくる。経済的には豊かである日本はどうなのだろうか。。。それはさておき、バウルとは何か。本書を読んでもおそらくその片鱗に触れただけなのだろうと思うが、何か人間の魂を解き放った先にあるものというか、俗っぽさと洗練さとが入り混じった人間の営みという感じだ。2014/12/03
-
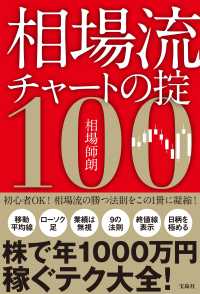
- 和書
- 相場流チャートの掟100