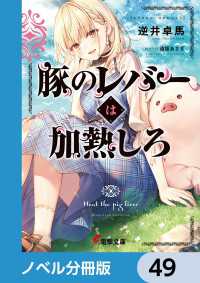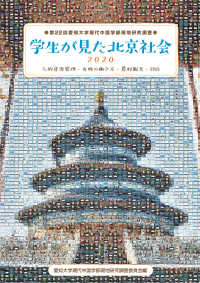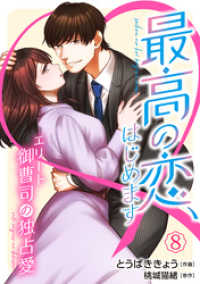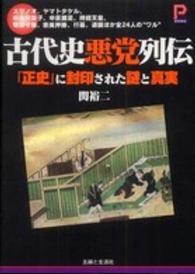目次
第1章 落語、この素晴らしきもの(人間の「業」とは何か;落語は「非常識」を肯定する ほか)
第2章 「自我」は「非常識」をも凌駕する(「自我」を発散する滑稽噺;“そのワンフレーズ”のために ほか)
第3章 “それ”を落語家が捨てるのか(軽蔑の言葉にもなる「上手い」;どこが上手いのか判らない ほか)
第4章 そして、三語楼へとたどりつく(「金語楼が欲しいなあ」;文楽と小さんだけは判らない ほか)
第5章 芸は、客のために演るものなのか(客もグロテスクを喜ぶ;よみうりホール『芝浜』の真意 ほか)
著者等紹介
立川談志[タテカワダンシ]
落語家、落語立川流家元。1936年、東京に生まれる。本名、松岡克由。小学生のころから寄席に通い、落語に熱中する。16歳で五代目柳家小さんに入門、前座名「小よし」を経て、18歳で二つ目となり「小ゑん」。27歳で真打ちに昇進し、「五代目立川談志」を襲名する。1971年、参議院議員選挙に出馬し、全国区で当選、1977年まで国会議員をつとめる。1983年、真打ち制度などをめぐって落語協会と対立し、脱会。落語立川流を創設し、家元となる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
落語の愉しみ本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まさ
29
10年程前に読んでからずっと気になっていた一文が記憶にあったので、他市の図書館から取り寄せて読み直し。実際、その記憶がどの部分だったのかはわからずじまいなのだけど(苦笑)。それでも、10年前には気づかなかった部分も多々あった。落語論なのだけど、人為をどう受け容れるかを問うていると思う。読みやすい、というか聴きやすい1冊。2020/03/20
gtn
14
あれほど心酔していた志ん生について、著者は「ここ二年くらいで気が付いた」と重要な告白をしている。いわく、志ん生のすべてのもとは、初代柳家三語楼であると。三語楼のギャグをつかみ込んでいるとまで言っている。おそらく間違っていまい。タブーにルーズだったから、破廉恥だったから、志ん生はあそこまで売れたのだ。2018/02/15
スピリッツ
11
落語とは業の肯定、だそうです。言い換えると、落語とは非常識の肯定、だそうです。『現代落語論』を事前に読んでおけばよかったなあと後悔してます。全三部作らしいので暇を見つけて残りを読みたいです。2014/03/26
ツナ
10
「志村けんさんが死んだことが信じられない、まだ生きてるような気がする」という、つぶやきをどこかで見た。死してなお人の心に残っている、生きているということなのでしょうか。2023年で13回忌であった立川談志師匠。私は落語家さんといえば、すぐ談志師匠を思い浮かべます。でも、師匠の落語を聞いたのは亡くなって数年経ってからでした。そこがとても残念でならない。落語の枕で時事問題をよくイジっていた師匠。世の中を騒がす何かが起きたとき、師匠がいればなんて言っただろうと今でもよく思う。内容は重くないです。師匠そのまんま。2024/02/06
ふらん
10
談志さんの聞き書き的な本。無責任にも思える言いっ放しが、寄席でのマクラを聞いているよう。少しだけやけど、小噺が載ってたのも嬉しい。職安にて、男「私、子どもが12人いまして」「他にできることは?」2015/08/04