- ホーム
- > 和書
- > 児童
- > 読み物
- > 短編集・アンソロジー
出版社内容情報
死んでからも、自分の敷地を広げようと夜中に境界の石を持ってうろうろする亡者の話をはじめ、魂が救われないままにさまよったり、人間につきまとったりする幽霊の話。いったい幽霊は、どうすれば救われるのか、死んだあとはどうなるのか、人間の魂は肉体がほろびた後も永遠に生き続けるのでしょうか。たくさんある幽霊の昔話の中から、プロイスラーが13話選んで語ります。 小学校中学年~
著者等紹介
プロイスラー,オトフリート[プロイスラー,オトフリート][Preussler,Otfried]
1923年チェコのボヘミア地方のリベレツという町にドイツ人の子として生まれる。第二次世界大戦時一九歳でドイツ軍に入隊、五年間ソビエト軍の捕虜となる。1949年から、西ドイツ南部のシュロスベルグで小学校の教師をしながら創作をはじめる。1970年からは作家活動に専念、現代ドイツの代表的児童文学作家
佐々木田鶴子[ササキタズコ]
香川県に生まれる。早稲田大学文学部を卒業後、ドイツに六年間滞在。帰国後、M.エンデをはじめとする多数のドイツ児童文学や絵本の翻訳を手がける。東京都在住
スズキコージ[スズキコージ]
1948年、静岡県浜北市生まれ。二〇歳のとき、新宿歌舞伎町の路上で初個展を開く。1987年に「エンソくんきしゃにのる」(福音館書店)で小学館絵画賞、1989年「やまのディスコ」(架空社)で絵本にっぽん賞を受賞。東京都在住
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
98
プロイスラーが各地から収集した昔噺のシリーズ3で、今回は幽霊に関するものが多いようです。1と同様に13の話が収められていて作者による解説が同様に最初にあり楽しめました。日本とは異なり様々な幽霊が出てきます。「九本ぜんぶあたり」はボウリングの話で一番印象に残りました。アメリカでも昔、九柱戯という遊びがあったことを思い出しました。2025/04/16
mocha
98
ドイツに伝わる幽霊の話をプロイスラーが再話。キリスト教の時代のものは教訓めいたお話が多いように思うが、それ以前のゲルマン民族の伝承の方は感覚的で面白い。怖いもの、陽気なものなど幽霊といってもいろいろ。ラストの「ちびすけ、こっちへおいで」はとても温かい気持ちになれるお話だった。2017/07/11
ままこ
79
プロイスラー流に仕立て上げられた幽霊にまつわる昔話、伝説集。ゾッとする話からホッとする話まで色々。ここに登場する人物はその人らしい生き方をして、その人らしい結末をむかえている。『ちびすけ、こっちおいで』は温かい気持ちになって良かった。コラージュの装丁がユニーク。2018/08/16
☆よいこ
48
[降臨節の早朝礼拝]あの世からメッセージを[墓場のダンス]音楽を止めてはいけない[九本ぜんぶあたり!]ボウリング[神父の悪魔ばらい][石をどこにおけばいいか]ナイトキャップの小間物屋]うまくいった[ナイトキャップをかえせ]うまくいかなかった[真夜中の森の口笛]近づきたくない[うるさい小さな幽霊たち]ポルターガイスト[青いアグネス]いい幽霊は白くない[白い紳士の幽霊]ご先祖様[魂をはこぶ船][ちびすけ、こっちへおいで]ペルヒタかあさん▽10月のハロウィンに合わせて読むつもりが遅くなった。怖くない。2019/11/14
ニミッツクラス
33
【日本の夏は、やっぱり怪談】〈其の三・和洋折衷〉 13年(平成25)の税抜1300円の単行本8刷(初版04年)。小峰書店の児童書“プロイスラーの昔話”(全3巻)の第3弾。既刊「真夜中の鐘がなるとき(宝さがしの13の話)」「地獄の使いをよぶ呪文(悪魔と魔女の13の話)」よりは怪談しているが成人が読んで怖い話は無い。独国の幽霊話を一部翻案したが、結末は変えてない由。「九本ぜんぶ…」は骸骨幽霊が骨のピンと頭蓋骨の玉でボウリングする話…なぜピンが7本(当時9本)なのか、なぜ骨だけで動くのか気になる。★★★★☆☆2024/08/23
-

- 電子書籍
- なんもわからん双子育児 11話 ebo…
-
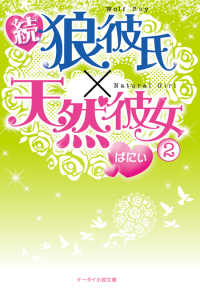
- 電子書籍
- 続 狼彼氏×天然彼女2 スターツ出版e…







