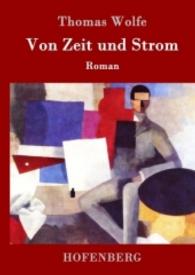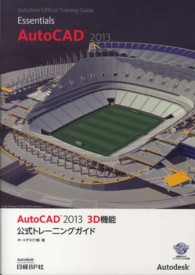出版社内容情報
なぜ木材から白い紙が? かんたんな実験や原子・分子模型から木の性質をさぐり、炭の利用から里山での人と自然との交流、森林との関係を考える。 小学校高学年~中学生
内容説明
紙の原料は木材だから、紙の回収とリサイクルが森林をまもることになる。森林はなぜ、まもっていかなくてはならないのだろう?環境のなかの森林の役割をさぐる。小学校高学年以上。
目次
木と紙
紙の分子=セルロース
植物とセルロース
セルロースの利用
炭をつくってみよう
薪と炭
木の建物や道具
日本の森
林業と森林
里山とくらし
いろいろな森の働き
森と環境
世界の森林と日本
森のあるまち
森をまもる
著者等紹介
板倉聖宣[イタクラキヨノブ]
仮説実験授業研究会代表。1930年東京の下町生まれ。東京大学で科学の歴史を研究して、1958年理学博士の学位を得て国立教育研究所に勤める。1963年“仮説実験授業”を提唱。1983年『たのしい授業』を創刊。評価論・教育史・発想法など広い分野の研究を推進して、社会の科学の研究・教育にも従事している
吉村七郎[ヨシムラシチロウ]
科学・環境教育研究家。1926年東京で生まれる。秋田鉱専冶金科卒。和歌山県中学校で理科、東京私立暁星小学校理科専科。国立教育研究所科学教育研究センター共同研究員、千葉大学教育学部非常勤講師などを歴任。仮説実験授業研究会発足当初より科学の授業書を作成。長年環境関係の授業書作成と、環境意識の高揚のための講演活動・環境とリサイクルの実践活動に関わる
荒井公毅[アライキミタケ]
足立区立関原小学校教諭。1955年東京都足立区に生まれる。東京学芸大学教育学部(理科専攻)を卒業後、国立市国立第八小学校、目黒第七中学校、文京区関口台町小学校を経て、現任校に勤務。1974年に他学部から教育学部に転学したとき、創刊されたばかりの教育雑誌『のびのび』を読み、板倉聖宣氏を知り“仮説実験授業”と出会う。授業研究を通して、授業書作成に携わり、算数の授業に仮説実験授業の考え方を持ち込む研究を進める
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
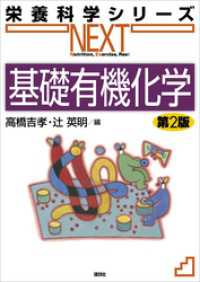
- 電子書籍
- 基礎有機化学 第2版 栄養科学シリーズ…