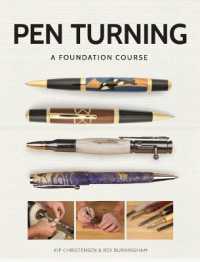- ホーム
- > 和書
- > 教育
- > 教育問題
- > いじめ・非行・不登校・引きこもり
目次
第1章 いじめ解決への新しい道筋(空白のいじめの指導24年間;いじめの指導の実際 ほか)
第2章 子ども裁判(学級開きから子ども裁判の開廷まで;子ども裁判の開廷から閉廷まで)
第3章 子ども裁判と担任の役割(担任の役割;相談者のカウンセリング ほか)
第4章 子ども裁判の実践(実践事例―口を閉ざした生徒;実践事例―何でも決めつける先生 ほか)
第5章 Q&Aコーナー(子ども裁判はどれだけ効果があるのでしょうか?;子ども裁判は学力低下にどう対応しますか? ほか)
著者等紹介
平墳雅弘[ヒラツカマサヒロ]
1956年生まれ、静岡大学教育学部卒業後、岐阜県の公立中学校教諭を経て、2007年より大垣市立北小学校教諭に。子ども裁判の実践で2003年に中日教育賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さとちゃん
0
ようやく読了。これが万能だとは思わないが(著者もそう断っている)、各学校に導入されたら良いな。もっとも、政府は本当に自分で考える人材を大量生産つもりはないのだろうから、難しいだろうな。2014/07/07
マーチャ
0
話がまるで出来ないいじめの状態の中では、アンケートから知ることは出来ないだろうと感じてしまう。インタビューして気持ちを表出できるくらいなら問題も深刻化しないし、陰湿ないじめは闇に閉ざされない。ただ、客観的に自分を見つめ直す時間を持てなければ反省も克服する勇気も湧いてこない。裁判という制度を知ることには意義も感じる。しかし、一歩間違えば取り返しがつかない危険性も伴う。親がそれらの経過を知ることや本人に事実を認識してもらう家庭を大事に出来る方法はないものか、考えさせてもらえた。2021/04/14
-

- 和書
- 街・魚景色