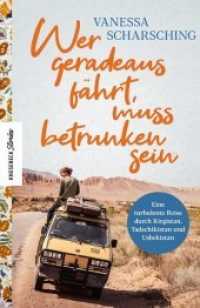目次
第1章 授業を創る(単元を構成する;「かしこい子ども」を育てる調べ学習;調べ学習の指導過程(国語科) ほか)
第2章 学習プランと図書館のかかわり(「調べ学習」を支える担任・司書教諭・学校司書の役割;調べる楽しさ、伝える喜び―3年生の調べ学習「生き物のふしぎを調べて、作文で伝える」;熱い思いを重ねて―5年生の調べ学習「日本語の泉」 ほか)
第3章 図書館活用教育の授業実践 各学年(第1学年国語科―「はたらくじどう車」について、調べたことを作文に書く;第2学年国語科―生き物の本を読んで、生き物広場を作る;第3学年国語科―生き物のふしぎを調べて、作文で伝える ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
杏子
19
またしても読むだけでお腹いっぱい状態に…。何度も言うが、こういうことは学校司書の努力だけでは何にもならない。協力して一緒に取り組んでくれる相手がいないことにはどうしようもない。司書教諭の先生が仕事をしてくれないことには、動くこともできない。詳しくは省くけど、勤務校にはそういう視点で動く方はおられない。図書館は学校のひとつの部門で特別扱いはしませんという考え方。なんか違う…違うが嘆くばかりで、何にもやらないのはしょうもないのでできそうなこと、小さなことくらいはやってみようかな。2016/08/10
ris3901
1
○斜め読み。読書センターとしてではなく、主に学習・情報センターとして教諭主導で学校図書館を活用する事例。専任司書として補助する立場なら読むと良いかと思う。盛り沢山で感嘆するレベル。2006年4月初版。2017/02/13