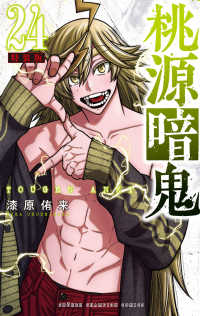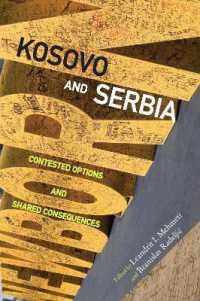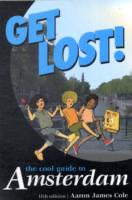- ホーム
- > 和書
- > 児童
- > 学習
- > 文明・文化・歴史・宗教
目次
第1章 紅茶のルーツをさぐる
第2章 紅茶の流行の始まり
第3章 紅茶が動かした大英帝国
第4章 アメリカ人と紅茶
第5章 ワカマツ・ティー・コロニー
第6章 ニッポン紅茶の生まれるまで
著者等紹介
千野境子[チノケイコ]
横浜に生まれる。早稲田大学第一文学部卒業。1967年産経新聞社入社。マニラ特派員、ニューヨーク支局長、女性初の外信部長、論説委員長などを経て現在特別記者兼論説委員。東南アジア報道で1997年度ボーン上田記念国際記者賞受賞。日米文化教育交流会議(カルコン)日本側委員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。