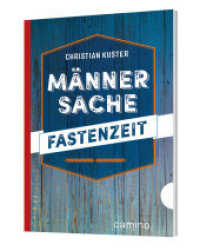内容説明
「進化」の最重要トピックス。アリストテレスの「自然の階段」からはじまり、ダーウィンの『種の起原』が革命を起こした、進化にまつわる仮説の数々。分子系統学の登場で新たな時代を迎えた“進化学の現在”までを、探求の道をともに歩んだ研究者たちとのエピソードを交え、生物学的に空間、大陸移動などの地球科学的な時間軸の絡みあいのなかにつむぐ、38億年の壮大な「進化」のストーリー!
目次
第1章 進化論の歴史
第2章 進化と地理的分布
第3章 進化と発生
第4章 すべての生き物の共通祖先
第5章 絶滅と進化
第6章 恐竜の世界から哺乳類、ヒトの世界へ
著者等紹介
長谷川政美[ハセガワマサミ]
分子系統学者。1944年新潟県生まれ。1966年東北大学理学部物理学科卒業、1970年名古屋大学大学院理学研究科博士課程中退。同年、東京大学理学部助手。統計数理研究所助教授を経て教授。その後、復旦大学(上海)教授を経て、統計数理研究所名誉教授、総合研究大学院大学名誉教授。理学博士(東京大学)。1993年日本科学読物賞、1999年日本遺伝学会木原賞、2005年日本進化学会賞・木村資生記念学術賞など受賞歴多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
hal
13
進化に関する様々なジャンルの研究のダイジェストが楽しめる一冊。是非手元に置いておきたい。もっとも不得意分野の話はかなり難しくて理解できたとは言えなかったかも。人間と一番近い親戚のチンパンジーは瞬間記憶能力があるとか。人間の自閉症スペクトラムの人の中にもそのような能力を持つ人がいる。自閉症のような障害や統合失調症の人は、どんな民族にも一定数いて、進化の中で淘汰されていない。それは、人類が生き抜く上で必要な人材だったからではないかという話は感動した。2021/01/22
スプリント
10
進化に関する研究を簡潔にまとめて編纂されています。 やや難解なところもあり完全に理解したわけではありませんが進化に潜む偶然と必然の神秘に触れることができました。2021/07/28
izumone
2
「万華鏡のような」という形容があるが,生物をめぐる人類の知見をきらめく切り口で満喫できる一冊。進化論の思想から,地球と生命の進化史,エボデボやDNAの構造と振る舞い,そして生物マンダラまで扱う内容は多彩。生物も,LUCA,3ドメイン,真核生物のスーパーグループから昆虫,哺乳類,ヒトまで,いろいろなレベルで「総登場」。自分として最も興味深かったのは,体重による種数の分布が恐竜類と鳥類・哺乳類とで異なるパターンを示すこと。グループ間の競争による進化の進化の歴史を跡づけるものらしい。今年読んだ科学本のベスト。2020/11/01
みう
1
分子系統学や生物についての知識が増えました。2024/04/01
-
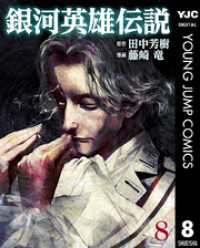
- 電子書籍
- 銀河英雄伝説 8 ヤングジャンプコミッ…