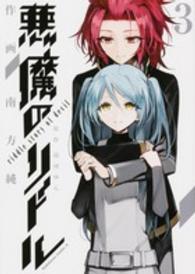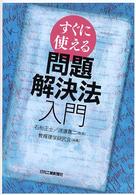出版社内容情報
明治21年から昭和20年まで170個もの師団を編成した帝国陸軍。その師団の編制の変遷と多様化、動員や編成の手法などを詳述。明治21年から昭和20年の敗戦まで戦略単位として170個もの師団を編成した帝国陸軍。その師団の編制の変遷と多様化、動員や編成の手法などを主なテーマとしながら、原則として県単位毎に徴集した壮丁で部隊を編成したことによってそれぞれの地域性が鮮明となり、それが各師団の特性となり師団の運用に影響を与えたことを豊富な史資料とともに詳述。巻末には4鎮台設置から敗戦までの師団編制表や師団配備に関する付表27点を付し、あわせて26頁にわたる明治2年の兵部省設置から昭和20年の第1復員省の発足までの師団関連略年表を付した。帝国陸軍の師団の全貌を記した1冊。
◆はじめに
◆第一章 国軍の草創期
薩摩の「近歩一」、長州の「近歩二」
特異な存在だった近衛師団
色濃く残った幕藩の気風
鎮台の拡充と西方シフト
徴兵制度と地域性
◆第二章 師団改編と連隊区制
「師団」の概念と編制の概要
連隊区制から生まれる郷土部隊
農村部の部隊と都市部の部隊
各兵科が求めた壮丁の資質
◆第三章 日清戦争と日露戦争
七個師団体制での日清戦争
常設師団十三個の根拠
熟考された五個師団の増設
日露戦争で定まった師団の評価
◆第四章 停滞した陸軍軍備
日露戦争後の軍備拡張
『帝国国防方針』の数値目標
動員制度の概要
大正の軍備整理と十七個師団体制
師管の変化と「一等師団」という存在
◆第五章 「一号軍備」と支那事変
破綻した対ソ戦備
「一号軍備」で生まれた三単位師団
想定外の大動員
民衆の海の中での戦争
◆第六章 多様化した師団の編制
「二号軍備」と「三号軍備」
関東軍の新編師団と「関特演」
南方向けの自動車編制師団
「四号軍備」と「軍容刷新計画」
治安師団と戦車師団の新編
絶対国防圏に対応する海洋編制師団
◆第七章 大陸、南方、満州の三正面作戦
常勝支那派遣軍を支えた古豪師団
酷使され続けた精強上陸兵団
ビルマ戦線の雄、「菊」と「龍」
形にならなかった陸海軍統合作戦
郷土部隊の真価を発揮した野州兵団
健闘した集成の小笠原兵団
「対ソ静謐」関東軍の消長
◆第八章 本土決戦の兵団群
等閑視されて来た本土防衛
結末は「根こそぎ動員」
「守地即死地」の沿岸配備師団
機動打撃師団と決戦兵団
郷土部隊による本土防衛
大動員の総決算
◆おわりに
◆引用・参考文献一覧
◆付表1?27
◆帝国陸軍師団関連略年表
藤井非三四[フジイヒサシ]
著・文・その他
内容説明
明治建軍から昭和20年の敗戦まで、日本が国力を振り絞って整備した師団群の特質と編制の変遷。
目次
第1章 国軍の草創期
第2章 師団改編と連隊区制
第3章 日清戦争と日露戦争
第4章 停滞した陸軍軍備
第5章 「一号軍備」と支那事変
第6章 多様化した師団の編制
第7章 大陸、南方、満州の三正面作戦
第8章 本土決戦の兵団群
著者等紹介
藤井非三四[フジイヒサシ]
軍事史研究家。1950年、神奈川県生まれ。中央大学法学部法律学科卒業。国士舘大学大学院政治学研究科修士課程修了(朝鮮現代史専攻)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nnpusnsn1945
六点
フロム
CTC
クラムボン