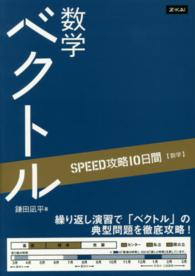出版社内容情報
日本と蘭印をめぐる状況分析。インドネシアと日本の新たな関係構築の必要性を論じ、決戦前夜の緊迫した情勢を伝える。
本書は、戦前日本の思想的指導者であった仲小路彰による蘭領インドネシアをめぐる状況分析である。1930年代当時、オランダ領であったインドネシアをめぐり、日本と英蘭の対立が激化。インドネシアと日本の歴史的関係、徳川幕府による鎖国、インドネシアが蘭領となるまでの経緯、インドネシア民族独立運動等についての分析と考察、そしてインドネシアと日本の新たな関係構築の必要性を論じ、決戦前夜の緊迫した情勢を伝える。
第一篇 日本南方圏と鎖国
第一章 鎖国の前夜
第二章 鎖国断行
第三章 じゃがたら文
第二篇 第十七世紀における白人侵略
第一章 第十七世紀中葉の形成
第二章 オランダの繁栄
第三章 十七世紀の情勢
第三篇 第十八世紀のオランダの搾取
第一章 植民地政策
第二章 支那人の大虐殺
第三章 イギリスの発展
第四章 イギリス、オランダの抗争
第五章 オランダ東インド会社の衰頽
第四篇 第十九世紀の植民地的弾圧
第一章 オランダ政府の直轄化
第二章 英仏の抗争
第三章 ジャワの蘭領化
第四章 オランダ商事会社の設立
第五章 強制耕作法の制定
第六章 植民地の反乱
第七章 侵略の強化
第八章 強制労働の反抗
第九章 植民地政策の変化
第五篇 第二十世紀初期の情勢
第一章 植民地制の確立と反抗
第二章 ランダー事件
第三章 反植民地的独立運動の激化
第六篇 東インドの土民
第一章 人口問題
第二章 インドネシア民族問題
第三章 スマトラの土民
第四章 ボルネオの土民
第五章 支那人問題
第七篇 北ボルネオの英国侵略
第一章 ボルネオのサラワク
第二章 第一代の国王ジェームス・ブルック
第八篇 オランダの植民地統治
第一章 オランダ統治法
第二章 中央行政府
第三章 国民参議会
第四章 地方行政
第五章 土地制度
第六章 貨幣制度
第七章 蘭印の軍備
第八章 植民政策の発展
第九篇 インドネシア民族独立運動の展開
第一章 ジャワ人の覚醒
第二章 サリカット・イスラム
第三章 土民の諸政党
第四章 社会主義運動
第五章 民族運動の発展
第六章 民族運動の弾圧
第七章 民族教育問題
第八章 土民法律問題
第十篇 蘭領インドの経済戦
第一章 金融制覇
第二章 国際投資戦
第三章 貿易戦争
【著者紹介】
明治34年東京生まれ。旧制五校、京帝大哲学科卒。昭和12年から「世界史話大成」「世界興廃大戦史」などの大著に取り組む。戦後著書はGHQに没収され一時公職を追放される。間もなく地球主義、未来学という概念を提唱。「ロシア大革命史」「未来学原論」などの大著を刊行。山中湖村に隠棲しつつも戦後の外交に隠然たる影響を与えた。
内容説明
GHQが没収した問題の書!!インドネシアが蘭領となった経緯、民族独立運動…インドネシアと日本の歴史的関係、新たな関係構築の必要性を論じ、列強との決戦前夜の緊迫した情勢を伝える。
目次
第1篇 日本南方圈と鎖國
第2篇 第十七世紀における白人侵略
第3篇 第十八世紀のオランダの搾取
第4篇 第十九世紀の植民地的彈壓
第5篇 第二十世紀初期の情勢
第6篇 東インドの土民
第7篇 北ボルネオの英國侵略
第8篇 オランダの植民地統治
第9篇 インドネシア民族獨立運動の展開
第10篇 蘭領インドの經濟戰
著者等紹介
仲小路彰[ナカショウジアキラ]
明治34年(1901)東京生まれ。父、廉(第3次桂・寺内国内閣の農商務大臣)の次男。大正6年(1917)第五高等学校入学、大正13年、東京帝国大学文学部哲学科卒。大正11年(1922)東京帝大在学中に、長編戯曲「砂漠の光」を新光社より刊行。昭和16年(1941)(財)日本世界文化復興会(終戦後、文化建設会と改称)を設立。昭和19年(1944)山梨県山中湖村に疎開。昭和20年(1945)「我等斯ク信ズ」を執筆、配布。陸海軍に「承詔必謹」を説き、米ソ冷戦時代を予告し戦後復興の方向を示す。昭和21年(1946)渋沢敬三・川添浩史等と(財)文化建設会の地球文化研究所設立。昭和59年(1984)9月1日、半生を過ごした山中湖村で死去。享年83歳(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。