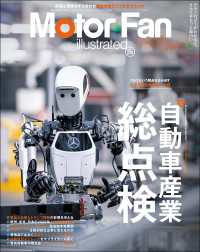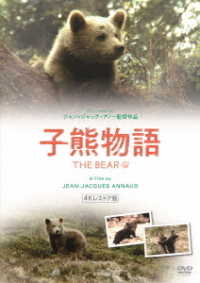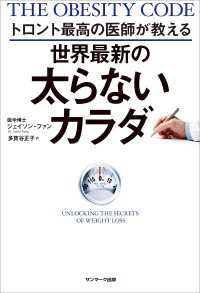- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 哲学・思想
- > 日本の哲学・思想(近世)
出版社内容情報
「義、忠、孝」。武士道精神とは、人としてもつべき心得のことである。日本人の倫理、武士道精神の歴史とその精髄を物語る。
「義」「忠」「孝」
武士道精神とは、人としてもつべき心得のことである。
菊池寛、平泉澄、渡辺世祐、吉田静致、清原貞雄、乙竹岩造、荒木貞夫、野村八良、近衛文麿、高木武が説く。
日本人の倫理的基盤として脈々と受け継がれてきた武士道精神を、歴史とともにその精髄を物語る。
「義」「忠」「孝」に代表される武士道精神は、刀を交えて戦う「武士」の心得の総称である。武士階級が消滅したあとも、日本人の倫理的基盤とされ脈々と受け継がれた。新渡戸稲造の『武士道』がはじめ欧米人向けに書かれていたのと異なり、本書は、刊行当時(昭和14年)の日本人自身に向けて、武士道の教えや武士道精神の歴史を平明に語ったものである。収録内容は、?@ 武士の発生と、武士道発達の歴史?A 江戸初期の山鹿素行による、儒教倫理にもとづく新しい「士道」の提唱とその影響?B 山本常朝述『葉隠』にみる武士の心得?C 幕末の吉田松陰『士規七則』に代表される、勤王思想の系譜と武士道?D 明治以降の近代日本の精神的支柱としての「武士道精神」などの論考を網羅したものである。
収録作品中、菊池寛による「武士道の話」は、戦国時代から昭和までの、人々によく知られた出来事を例に、そこに武士道精神がどのように現れているかを読む。「葉隠」のもっとも平明な解説となっている。また、平泉澄による「桜と武士道」は、武士と桜との関わりを考察し、武士道としてだけでなく、日本人論として読むことができる。
内容説明
武士道精神とは、人としてもつべき心得のことである。日本人の倫理的基盤として受け継がれてきた武士道精神を、歴史とともにその精髄を物語る。
目次
1 武士の起源と武士道(渡辺世祐)
2 武士道の根本精神(吉田静致)
3 武士道の神髄(平泉澄)
4 武士道の話(菊池寛)
5 山鹿素行の武士道(清原貞雄)
6 葉隠に現れた武士道(乙竹岩造)
7 物のあわれと武士道(野村八良)
8 日本武士道と西洋武士道(高木武)
9 名将を語る(荒木貞夫)
10 国体と武士道(近衛文麿)