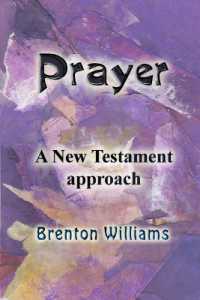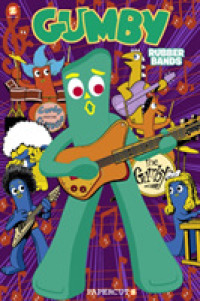感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
雪紫
30
2人が死に、中盤でまさかの容疑者が逮捕され、裁判物へ(ここから読むペースが上がる)。容疑者が容疑者だからかあの人物が犯人か否かさえ、わからないままに衝撃のラストへ・・・って、なんだこのエピローグは?似た形式のミステリや趣向は見るようになったけど、それでもどう言葉にすれば良いかいまいちわからない怪作。・・・って、解説すら更に怪作にさせる手助けしてるー!?2020/05/18
gu
7
思っていた以上に奇書系だった。もしくは現代文学寄りの人が書いた探偵小説のパロディ。奇書とは言っても日本におけるそれのようにおどろおどろしい舞台装置は出てこず、下世話な現代劇に終始するところが(登場人物の一人の元ネタである)ジョイスの『ユリシーズ』を思わせる。文芸批評を交えたメタな仕掛けや真相の解明そのものを放棄しているところは嫌いじゃないけど、この小説が面白いのかはよくわからない2020/07/03
飛鳥栄司@がんサバイバー
7
ぐるぐる回る。同じことが繰り返されるグルグルと、裁判での訴追側の根拠の無さと被告側の完璧な反論で立場がグルグルするのと、主人公マケイブと刑事スミスのやりとりのグルグルと、エピローグで語られるミステリ(探偵小説)の解説がグルグル。なんと言っても、読後、整理しきれない何かが頭の中をグルグル回る不思議な感覚。結局、どこにでも着地できる要素がなければ探偵小説ではないし、探偵小説だからこそどこにでも着地できるのだという結論をメタで表現している、神から目線の超絶小説ということでいいのだろう。自分には消化不良な作品。2013/11/26
とぶとり
7
ピエール・バイヤールが「アクロイドを殺したのは~」で主張した、ミステリという閉じられた構造を開かれたテクストとしていく作業を、読者ではなく作者が意図的に行っていこうとした作品。1937年発表というあまりにも早すぎたため当時はまるで評価されず、近年再評価されているとか。「いかなる探偵小説にも、ありうべき結末の可能性は無限にある」2011/04/25
Genei-John
5
海外ミステリにも奇書があったのだなと思う。2014/08/02
-

- 洋書電子書籍
- Diagnostic Liquid-B…