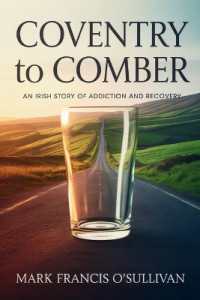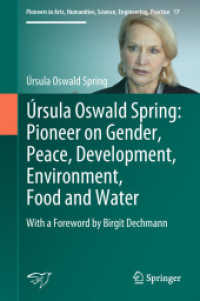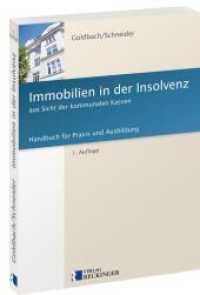出版社内容情報
戦後を代表する社会学者・作田啓一と見田宗介を対比的に論じることで現代日本社会のありようを根底から考え直す、力作揃いの論考。●現代社会学の新しい潮流をリードする!
作田啓一と見田宗介、この魅力溢れる二人の社会学者を対比的に論じ、日本社会学に新しい転換点をもたらす画期的な論考群。
斬新な試みによる、知の格闘技。
【本書「序章」より】
私たちは日本の社会学者がこれまでしてきた仕事をどれだけ知っているだろうか。それが達成したことを検討して、その可能性を評価し、限界を批判して、自分たちがなすべき仕事のために引き継ぐべきものを引き継ぐという作業を、私たちは行ってきただろうか。日本の社会学者たちが現実と格闘してつくりあげてきた成果を、私たち自身が人間と社会をより深く理解するために用いようとする工夫や努力を、どれくらい試みてきただろうか。
本書『作田啓一vs. 見田宗介』は、社会学者・作田啓一と見田宗介の仕事を理解・紹介し、ふたりの社会学を対比・検討し、それがどんな可能性をもち、いかなる限界があったかを評価・批判して、私たち自身が彼らの社会学からなにをどのように引き継げるかを考えようと試みたものである。
序章 作田啓一vs.見田宗介
――「日本の社会学」を研究する【奥村 隆】
?「日本の社会学」を研究する――本書にいたる経緯
?作田啓一/見田宗介とは誰か――素描的な紹介
?作田啓一 vs. 見田宗介――本書の構成
第1章 戦後社会の生成と価値の社会学
――作田啓一における「近代の超克」とその社会学的展開【出口剛司】
?近代の超克と一九六〇年代の作田
?近代の超克と封建遺制
?西洋近代と日本
?価値の社会学再考
第2章 見田宗介における「相乗性」という限界
──『近代日本の心情の歴史』を読み直す【長谷正人】
?土着の社会学──一九六〇年代の見田宗介
?内攻化された心情としての流行歌
?相乗的な心情としての流行歌
?相剋的な心情としての流行歌
?相剋性の文化へ
第3章 「移行期」の思想
――作田啓一と見田宗介の「個人」への問い【片上平二郎】
?移行期という問い――「社会学の生成」に立ち会うということ
?「真木悠介」とは誰のことか?――見田宗介の「移行期」
?「こぼれ落ちるもの」の軌跡と「個人」への問い――作田啓一の「移行期」
?「変身」の季節としての「移行期」
第4章 もう一つの時間の比較社会学
――真木悠介『時間の比較社会学』からの展開【鳥越信吾】
?はじめに
?第一の比較社会学??―抽象性と不可逆性
?第二の比較社会学??―時間のニヒリズム
?もう一つの比較社会学??―積み重なる時間
?「天空の地質学」への展開??―『宮沢賢治』の時間論
?横の比較社会学と縦の比較社会学
第5章 事件を描くとき
――〈外〉からの疎外と内なる〈外〉【小形道正】
?はじめに――殺人事件と日本の社会学
?社会構造に疎外された殺人――「まなざしの地獄」より
?自己の欲望に支配された殺人――「酒鬼薔薇少年の欲動」より
?時代診断と自律的言説の暴力
?人間と〈外〉をめぐる問い
?おわりに――〈外〉の現在性
第6章 「作田啓一/見田宗介の初期著作における「価値」
――「一九六〇年代の理論社会学」をめぐる知識社会学【鈴木洋仁】
?はじめに
?見田宗介『価値意識の理論 欲望と道徳の社会学』
?作田啓一『価値の社会学』
?「価値」をめぐる時代拘束性
?「価値」のその後と現在
第7章 〈リアル〉の探求
――作田啓一の生成の思想【岡崎宏樹】
?文学の感動と〈リアル〉
?〈第1期〉:学術論文/エッセイの二重戦略
?〈第2期〉:三次元の自我論
?〈第3期〉:力の思想
?おわりに
第8章 見田社会学におけるリアリティ【浅野智彦】
?リアリティという問題設定――見田社会学の三つの時期
?原理論・社会意識論におけるリアリティ――未来と主体の理論
?比較社会学におけるリアリティ――「世界」と〈世界〉の理論
?再開された原理論・社会意識論におけるリアリティ――ロジスティック曲線の理論
?おわりに
第9章 反転と残余
――ふたつの「自我の社会学」におけるふたつのラディカリズム【奥村 隆】
? はじめに――ふたつの「自我の社会学」
? まなざしのオブセッション――「恥と羞恥」と「まなざしの地獄」
? 自己革命のモノグラフ――『ルソー』と『宮沢賢治』
? 〈明晰〉なる反転――『自我の起原』
? 残余のラディカリズム――『生成の社会学をめざして』
奥村 隆[オクムラ タカシ]
内容説明
作田啓一と見田宗介、この魅力溢れる二人の社会学者を対比的に論じ、日本社会学に新しい転換点をもたらす画期的な論考群。
目次
1(戦後社会の生成と価値の社会学―作田啓一における「近代の超克」とその社会学的展開;見田宗介における「相乗性」という限界―『近代日本の心情の歴史』を読み直す)
2(「移行期」の思想―作田啓一と見田宗介の「個人」への問い;もう一つの時間の比較社会学―真木悠介『時間の比較社会学』からの展開)
3(事件を描くとき―“外”からの疎外と内なる“外”;作田啓一/見田宗介の初期著作における「価値」―「一九六〇年代の理論社会学」をめぐる知識社会学)
4(“リアル”の探求―作田啓一の生成の思想;見田社会学におけるリアリティ)
5(反転と残余―ふたつの「自我の社会学」におけるふたつのラディカリズム)
著者等紹介
奥村隆[オクムラタカシ]
立教大学社会学部教授。1961年徳島県生まれ。東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。博士(社会学)。東京大学文学部助手、千葉大学文学部講師、助教授を経て現職。専攻はコミュニケーションの社会学、文化の社会学、社会学理論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
小鈴
小鈴
もっち
-

- 電子書籍
- 「頭がいい」とはどういうことか ――脳…