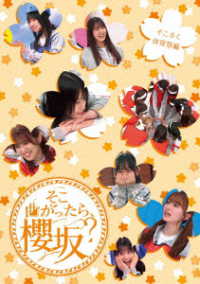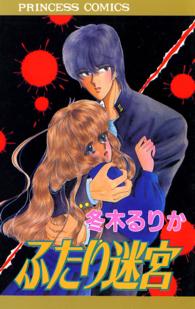内容説明
一九九五年の阪神・淡路大震災から始まった災害ボランティア活動は、二〇〇四年の新潟県中越地震などを経て日本社会に定着した。そして、二〇一一年の東日本大震災に遭遇した。そこで何が起きたのか?実践と学問の見事な達成によって、新しい社会の構想を提起する。
目次
第1章 東日本大震災と災害ボランティア
第2章 災害ボランティア研究
第3章 災害ボランティアの二〇年
第4章 救援活動と災害ボランティア
第5章 復興支援活動と災害ボランティア
第6章 地域防災活動と災害ボランティア
第7章 災害ボランティアが拓く新しい社会
著者等紹介
渥美公秀[アツミトモヒデ]
1961年大阪府生まれ。大阪大学人間科学部卒業。フルブライト奨学金によりミシガン大学大学院に留学、博士号(Ph.D.心理学)取得。大阪大学大学院人間科学研究科博士課程単位取得。神戸大学文学部助教授、大阪大学大学院人間科学研究科助教授などを経て、2010年大阪大学大学院人間科学研究科教授。自宅のあった西宮市で阪神・淡路大震災に遭い、避難所などでボランティア活動に参加。これをきっかけに災害ボランティア活動の研究と実践を続けている。特定非営利活動法人日本災害救援ボランティアネットワーク理事長のほか、日本グループ・ダイナミックス学会や日本自然災害学会の学会役員を務めている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おさむ
32
阪神大震災で被災したのを機に、災害ボランティアの研究と実践を伝えている著者。斜め読みだが、大学教授がとてもまじめに書いている印象。この20年間で日本のボランティアがいかに浸透してきたかがわかる。被災者によって逆に助けられるという反転の経験がボランティア活動の原点。しかし、知らぬ間に秩序化のドライブに巻き込まれて、既存の体制に取り込まれていくことへの違和感を指摘する。それが東日本大震災での初動の遅れに繋がったとする主張は一理ある。被災地リレーによって各地の被災者が想いを共有できるのは良い試みですね。2018/12/08
1.3manen
15
社会科学は、解釈の多様性をもとに 言説の豊かさを高めるので、 物語科学である。 社会科学は、認識科学である(72頁)。 心のケアに訪れた臨床心理士は、 被災者からは不評、拒否的とのこと。 小沢牧子先生は、こころの専門家という名の 資格を増やし、心理を産業化させることは、 被災者のためではなく、専門家自身の ためではないか、と手厳しい(100頁)。 本来の心のケアは、地域社会や共同体という 集合体が再構築されていく過程を、 被災者とともに構築することによって 支援していく(103頁)。 2014/06/21
takao
1
ふむ2021/12/16
なさぎ
1
昨今の日本に蔓延する結果至上主義に対し、強烈な反証を示す。10年単位での関係性の構築、その結果得られた学問的知見も、予見的に掴んでいたものでもなければ、打算的に狙いに行ったわけでもない。ただ被災された方々に「何か自分にできることは」と寄り添う思い、それこそが、他では得られないフィールドとの信頼関係を結果的にもたらしたまでのこと。こうした豊かな研究は、今後の日本ではどんどん少なくなっていくのだろうか。2019/09/04