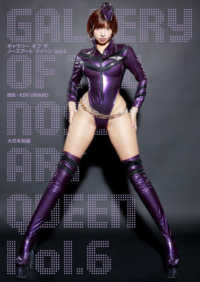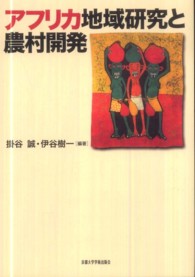内容説明
ロボットが事故を起こしたら?ヒトを傷つけたら?「感情」を持ったら?―AI技術の進展で急浮上する数々の難問を“制御不可能性”と“不透明性”を軸にときほぐし、著名文芸作品や映画作品等にも触れながら、ロボットがもたらしうる法的論点を明快に整理・紹介。日本における「ロボット法」の礎となる、第一人者による決定版。
目次
序章―ロボット法の必要性
第1章 ロボット工学3原則
第2章 ロボットの起源と文化
第3章 ロボットの定義と特徴
第4章 ロボットの種類とその法的問題
第5章 ロボット法の核心―制御不可能性と不透明性を中心に
第6章 ロボットが感情を持つとき
著者等紹介
平野晋[ヒラノススム]
中央大学総合政策学部教授・同大学院総合政策研究科委員長。米国弁護士(ニューヨーク州)。1984年に中央大学法学部法律学科を卒業し、同年入社した富士重工業株式会社にて法務に携わり、コーネル大学大学院(コーネル・ロースクール)に企業派遣留学して1990年に修了(法学修士)。同年にニューヨーク州法曹資格試験を受験・合格。翌1991年に同大学院特別生(『コーネル国際法律雑誌』編集委員)。1995年からNTTグループ企業で法務に携わり、2000年から株式会社NTTドコモの法務室長。2004年から中央大学教授。2007年に博士号(総合政策)(中央大学)取得。コーネル・ロースクール留学以来、製造物責任法の世界的権威ジェームズ・A.ヘンダーソンJr.教授から教えを受ける。経済産業省「ロボット政策研究会」(2005~2006年)を含む政府有識者会議を多数歴任。総務省「AIネットワーク社会推進会議」幹事、および「開発原則分科会」会長を務める(2016年~)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Tenouji
izw
kenitirokikuti
Hatann
anaggma