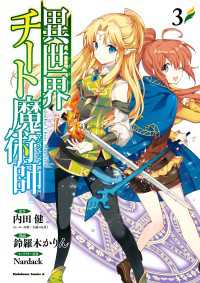出版社内容情報
中近世の神宮崇敬史を実態的に解明
伊勢御師とは伊勢神宮における私的な祈祷を担い、神宮の御祓大麻を各地に届け、各地の参詣人を神宮に案内し、宿を提供するなどの活動をした人々です。第一編ではあらゆる文献を博捜して全国的に活動していた御師の実像を詳らかにします。
一方で神宮では、宇治と山田に所在する内宮・外宮それぞれに文庫を設けて祠官の学問の進展と継承に努めまていました。第二編では神宮所蔵の古典籍を探求して神宮での学問の興隆と近代への継承を詳述します。
内容説明
中近世の神宮崇敬史を実態的に解明。伊勢信仰を担う御師の実像をあらゆる文献を博捜して明らかにし、神宮を担う祠官の学問の興隆と近代への継承を詳細に論述。
目次
第1編 伊勢御師の機能と展開(中世後期の伊勢御師の機能と展開;中世後期における伊勢御師三方家の存在形態(上)
中世後期における伊勢御師三方家の存在形態(中)
中世後期における伊勢御師三方家の存在形態(下)
伊勢御師と在地の関係性について―甲斐府中の町名変更を素材に
補論 宇治橋の歴史について)
第2編 宇治山田における学問の興隆と継承(近世宇治山田の学問形成;神宮の古典籍;神宮文庫の設立と神宮の編纂事業)
著者等紹介
窪寺恭秀[クボデラヤスヒデ]
昭和49年、山梨県生まれ。現在、神宮主事、神宮文庫勤務。教学課研究員、皇學館大学研究開発推進センター共同研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。