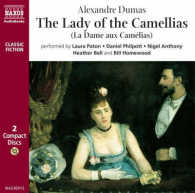出版社内容情報
式年遷宮の基礎はどのように築かれたのか。内宮祢宜・中川経雅、御巫清直の事蹟を丹念に跡づけて明らかにする。●式年遷宮の興隆はいかにもたらされたか
20年に1度行われる伊勢神宮の式年遷宮は、戦国時代の120年以上に及ぶ中断や幾度かの延期などはあったものの2013年の第62回まで、およそ1300年にわたって続き、現代でも遷宮年に限らず神宮は毎年800万人前後の参拝者を集めています。
このような興隆は、近世神宮考証学の基礎を築いた江戸時代後期の中川経雅、それを大成した幕末から明治に生きた御巫清直によってもたらされました。
経雅の『大神宮儀式解』『慈裔真語』、清直の『神朝尚史』『御饌殿事類鈔』などの著作を詳細に分析し、内宮と外宮の巨人の事蹟と思想の背景を丹念に考究した大作です。
●第一編 近世神宮考証学成立の過程(総論)――神宮古典系譜図について――
『神宮古典系譜図』
一 はじめに
二 古代(神代?平安)
三 中世(鎌倉?室町)
四 近世・近代(安土桃山?明治)
五 おわりに
●第二編 中川経雅の儀式研究
第一章 経雅の『大神宮儀式解』執筆
一 はじめに
二 中川経雅について
三 『儀式解』の執筆と神宮考証学の樹立
四 『儀式解』の特徴と本居宣長の『古事記傳』の影響
五 おわりに
第二章 経雅著『慈裔真語』について
一 はじめに
二 『慈裔真語』の成立と執筆の動機
三 『慈裔真語』の内容構成と分類
四 『慈裔真語』の執筆理念と儒学
五 おわりに
●第三編 御巫清直の研究
第一章 清直の神宮観――神朝廷論を中心として――
一 はじめに
二 御巫清直について
三 清直の神朝廷論
四 清直の皇大神宮相殿神論と職掌人(内人・物忌)考
五 清直の神嘗祭観
六 清直の外宮(トツミヤ)思考と豊受大御神の御霊実観
七 おわりに
第二章 清直著『神朝尚史』の研究
一 はじめに
二 『神朝尚史』の構成と内容
三 『歸正鈔』執筆の考証理念と『神朝尚史』の編纂
四 第五十六回式年遷宮と清直の神宮考証学における『神朝尚史』の位置
五 『神朝尚史』の成立と平田篤胤の『古史成文』の影響
六 おわりに
第三章 神宮常典御饌考――清直著『御饌殿事類鈔』を通して――
一 はじめに
二 外宮の御鎮座と御饌殿
三 御饌殿の殿舎及び神座(装束)と常典御饌の神饌
1 殿舎
2 神座(装束)
3 常典御饌の神饌
四 常典御饌の行事次第と総御饌
1 行事次第
2 総御饌
五 常典御饌の意義
1 常典御饌奏上祝詞
2 祭祀空間
六 おわりに
●補論 御巫清直考証神宮神事絵画について
一 齋内親王参宮圖
二 皇大神宮神嘗祭舊式祭典圖(奉幣之儀)
三 神宮考証学舊式遷御圖
吉川 竜実[ヨシカワ タツミ]
内容説明
式年遷宮の興隆はいかにもたらされたか。近世神宮考証学の基礎を築いた中川経雅、大成した御巫清直、その事蹟と思想の背景を丹念に考究する。
目次
第1編 近世神宮考証学成立の過程(総論)―神宮古典系譜図について(『神宮古典系譜図』)
第2編 中川経雅の儀式研究(経雅の『大神宮儀式解』執筆;経雅著『慈裔真語』について)
第3編 御巫清直の研究(清直の神宮観―神朝廷論を中心として;清直著『神朝尚史』の研究;神宮常典御饌考―清直著『御饌殿事類鈔』を通して;御巫清直考証神宮神事絵画について)
著者等紹介
吉川竜実[ヨシカワタツミ]
昭和39年、大阪府生まれ。平成元年、皇學館大学大学院文学研究科国史学専攻修士課程修了。現在、神宮権禰宜、神宮司庁祭儀部儀式課長兼考証課長・神宝装束課長兼教学課主任研究員、皇學館大学非常勤講師。平成11年1月第1回神宮大宮司学術奨励賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- ひらがな真宗