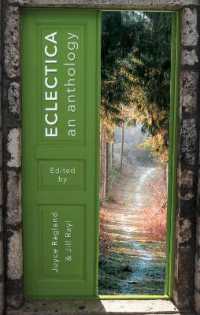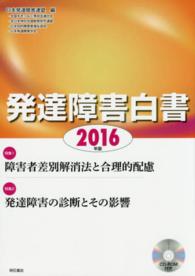内容説明
いま初めて明かされる“権力共同体”の内幕!世界はこの6000人に支配されている!!
目次
序章 パワー・エリートたちの散歩道
第1章 それぞれが百万人に一人の逸材―スーパークラスに会ってみる
第2章 不平等な世界―不平等、反発、新しい秩序
第3章 歴史の教訓―エリートの興亡
第4章 多国籍化の時代―金融と経済がすべての中心になったとき
第5章 世界主義者vs.国家主義者―新世紀に向けての政治的争点
第6章 非対称の時代―巨人の衰退と影の軍団の隆盛
第7章 情報スーパークラス:知識の力
第8章 スーパークラスのメンバーになる方法―成功の神話、現実、精神病理学
第9章 スーパークラスの未来―われわれにとっての意味
著者等紹介
ロスコフ,デヴィッド[ロスコフ,デヴィッド][Rothkopf,David]
米コロンビア大学ジャーナリズム大学院を卒業後、インターナショナル・メディア・パートナーズを設立・経営。新興国市場関係の新聞・雑誌の発行に携わる。その後、アメリカ商務省の国際貿易担当副次官としてクリントン政権に参加。公職を退いた後、キッシンジャー・アソシエーツの取締役を経て、国際問題に関する情報コンサルタント会社インテリブリッジを設立。同社売却後に書いた前著『Running the World:The Inside Story of the National Security Council And the Architects of American Power』は各方面で高い評価を得た。現在は国際コンサルタント会社ガーテン・ロスコフ社の社長兼CEOのほか、カーネギー国際平和財団客員研究員、コロンビア大学国際公共政策大学院講師などを務める。国際問題および新興国市場の専門家としてニューヨーク・タイムズ、ワシントン・ポスト、フィナンシャル・タイムズ、フォーリン・アフェアーズなど、主要な新聞・雑誌に多数寄稿している
河野純治[コウノジュンジ]
1962年生まれ。明治大学法学部法律学科卒業。翻訳家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
もくたつ(目標達成)
鬼山とんぼ
hiyu
壱萬参仟縁
いかちょー