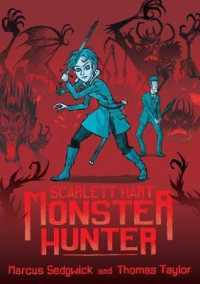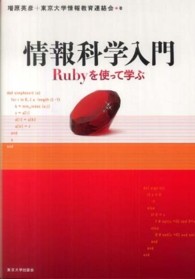内容説明
衛星放送の画面のなかで撃ち殺される少年。放送を阻止するため、首都に大停電を起こしたリビア。五〇〇ポンド爆弾で吹き飛ばされ、ミサイルを撃ち込まれる支局。CIAの手先か、テロリストの宣伝機関か。クレームによる各国大使の召還と、国交断絶の嵐。それでもアルジャジーラは、姿勢をつらぬいた…。「これはテレビ戦争であり、テレビそのものが戦場になっている」この惨劇の真の犠牲者は、ジャーナリズムそのものだ。9.11、インティファーダ、タリバン、イスラム過激派、イラク戦争…。一つの主張があれば、また別の主張がある。我々はすべてを伝える。「もっともすぐれた戦争報道はどこかって?アルジャジーラを見てごらん」。
目次
砂漠の小さな放送局
電波の種、中東に蒔かれる
アラブ世界への衝撃
反イスラエル闘争の真実
9・11はメディア戦争だ
アフガニスタンとタリバン
アルジャジーラかCNNか
「現場にいなけりゃ仕事にならん」
イラク戦争、特派員の殉職
テロリストに電波を利用させる?
アラブ人と言論の自由
英語放送は未来を開く
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
クチバシ
6
日本じゃ知らない人も多いだろうな。現に自分もアルジャジーラなんて言葉はこの本を読むまで知らなかった。読み終えた後は、アメリカ卑怯なりと思ったが、「一つの意見があれば、また別の意見がある」ということを思い出して、アメリカにも正義があるのだと思い直した。西アジアのことを日本人はほとんど知らないので、一読しても損は無いかと。2011/12/18
CCC
5
「一つの意見があれば別の意見がある」、つまりは両論併記という事ですね。アルジャジーラ、名前と一部報道くらいは聞いたことはありましたが、そういうモットーを持っているというのは知りませんでした。面白い。しかし旗幟を鮮明にしないと、結局周囲全てが敵になるという話も聞きますが、途中まで全くその通りの流れだったような気がします。中立性を保つのは辛い。ただまあ実際どれだけ中立かは分からないんですが。この本は明らかにアルジャジーラ寄りですしおすし。モットーに引きずられたわけじゃないけれど、別の意見も聞きたくなりました。2016/02/17
河合晋輔
5
約10年前に発刊された本ですが現代の中東情勢を知るには必読かもしれません。同時にジャーナリズムと報道、体制側のプロパガンダの実態がよくわかります。2014/12/31
makimakimasa
4
著者はサウジアラビア生まれのイギリス人フリージャーナリスト(中東問題専門)。ややアルジャジーラに肩入れしている気もするが、その不屈のジャーナリズム精神はよく理解出来た。まさに、全てを敵に回したテレビ局だ。その後、赤字は解消したのだろうか(本書は2005年出版、資金源であったカタールのハマド首長はWikipediaで見ると昨年亡くなっている)。分厚い内容は丹念な取材に基づいており、当時の政治リーダー(カダフィやシャロンやブレアなど)のエピソードが豊富で、また湾岸諸国などアラブ各国の関係性も見えて面白かった。2014/04/23
にゃおまる
3
ボリューム満点!時間がかかってしまったが、興味深い! アラブの小国カタールからこんな面白いメディアが産まれていたとは。アラブの常識を破り権力者に片寄らず事実だけを報道するメディアがあることを知り、自国の事を恥ずかしく思う。アメリカ、イギリスに検閲が入り、政府から圧力が掛かっているとは…もうアメリカは自由の国ではない。権力者に良いように事実は書き換えられ、プロパガンダされている。感想がそれていくが、アラブは今まさに戦国時代。王様がいるのは何となく知っていたけど、国は一族の物なんですね。2017/04/07