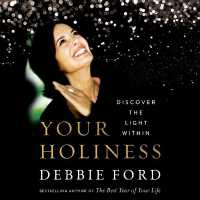- ホーム
- > 和書
- > 教養
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
内容説明
東京・六本木に美術館が立て続けにオープンし、村上隆のフィギュア作品が16億円で落札されるなど、今、東京のアートシーンは大きく盛り上がっていると言われる。だが、それはごく限られた一部での話だ。実際は、世界的に美術品が高騰しているなかで、日本だけが取り残されている。アメリカやヨーロッパに限らずアジアでも、人気があるのは中国や韓国の美術作品ばかりなのだ。銀座にあった多くの画廊は有名ブランドに押され、次々に姿を消している。日本の美術界は、今、息も絶え絶えなのである。では、いったいどうしてそのような状況になってしまったのか?その答えは、日本人が「投資としての美術品」と「文化としての美術品」の区別がつかないからだ。きちんとした価値観がないから、世界から笑われる。このままでは、間違いなく日本が「アートの墓場」となるだろう。
目次
第1章 アートの墓場
第2章 テキトーに決められる美術品の価値
第3章 美術界にうごめく魑魅魍魎な人々
第4章 なにがコレクターの魅力なのか?
第5章 投資としての美術品
第6章 戦略としての美術品
著者等紹介
新美康明[ニイミヤスアキ]
メディア(美術展、出版、各種イベント等)プロデューサー、文筆家。1952年、名古屋市生まれ。美術雑誌の編集者等を経て独立。1985年、銀座に牧神画廊を開設。以来、主に美術の世界で様々なイベントや美術展を行う。長野オリンピックでは公式ポスターをプロデュース。文部科学省の学習指導要領の作成に民間人としてはじめて関わり、教育映画(文科省特選)の編集委員や国際児童画展の審査員としても活躍。日本感性教育学会の設立にも尽力し、理事を歴任する(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-

- 和書
- 落窪物語総索引