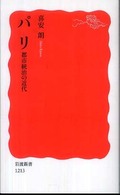出版社内容情報
1971年から2021年まで10年ごと、ニュータウンに住む人たちの視線で紡がれる連作短編集
内容説明
人々の大きな夢と希望を集め、郊外に開発された巨大な人工の町―若葉ニュータウン。高度経済成長、バブル景気、震災、そしてすぐそこの未来まで…。1971年から2021年までの10年ごとをニュータウンの住人たちの視点で紡ぐ、全六編の連作短編集!
著者等紹介
中澤日菜子[ナカザワヒナコ]
1969年東京都生まれ。慶應義塾大学文学部卒業。出版社に勤務しながら、劇作家として活躍。2007年「ミチユキ→キサラギ」で第3回仙台劇のまち戯曲賞大賞を受賞。2012年「春昼遊戯」で第4回泉鏡花記念金沢戯曲大賞優秀賞を受賞。2013年に『お父さんと伊藤さん』(応募時タイトル「柿の木、枇杷も木」)で第8回小説現代長編新人賞を受賞し、小説家としてデビュー(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ma-bo
96
中澤さんは初読み。2017年に刊行された作品。ニュータウン(巻末参考文献から多摩ニュータウン)を舞台にした連作短編集。高度経済成長、バブル景気、閉塞感、震災、すぐそこの未来。1971年~2021年までを10年ごとを1章にくぎりそこに住む(住んでいた)人達や街、時代の移り変わり、そしてニュータウンの問題も描いている。章ごとの人物達がゆるやかに繋がり、地元集落出身の公務員小島健児を軸に語られる物語。2025/09/13
ゆみねこ
96
東京郊外、おそらくは多摩ニュータウンの50年を描いた作品。一様に決まった企画の団地群が立ち並び始めた1971年から、バブル期を経て少子高齢化の進むニュータウン。公務員・小島健児を軸に語られる物語は、切なくて、でも少し明るい未来も見えて、とても良かったです。若葉=多摩、稲峰=稲城、松田=町田、桑都=八王子、分かりやすい!2017/09/04
ダミアン4号
92
“ニュータウン”を舞台に高度成長期からバブル期を経て現在、少し先の時代まで…そこに暮らした人々の生活を描いた連作短編。自分が育ち暮らした時代背景と重なる部分が多く、記憶の片隅に仕舞ってあった懐かしい風景を思い出しながら頁をめくりました。私の住んだニュータウン(団地)では“棟”毎の仲間意識みたいなものが強く…必然、子供達のグループもそれに合わせ分かれていた様に思います。なので、新しい友達が出来た時も「◯棟の◯◯ちゃん」みたいな表現をして(笑)少子高齢化が進みあの街の風景もこの物語の様に廃れてしまったのかな…2017/09/29
モルク
89
ニュータウンを舞台に1971~2021年までの50年間の住人たちを描く連作短編集。私も一戸建ての分譲住宅似たような家が並ぶ新興住宅地育ちなので、そこには懐かしい風景があった。ほぼ同時に入居した同世代の人々、急激に増えた住民で小学校が入りきれず転居してきた住人は隣の学区の小学校に間借りし電車通学をしていた。地域には子供の声が溢れていた。この物語と同じく今では高齢者であふれ、店舗もどんどん撤退し高齢者にとって不便な地と変わっている。この物語の最後のように光が少しでも差して来るところになれば…と思う。2017/10/25
fwhd8325
88
私は東京の下町と言われる場所で生まれ、育ってきたので「ニュータウン」という街の巨大な団地がそびえる風景は、別世界のように感じていました。最近、ニュータウンの老朽化、暮らす方々の高齢化が取り上げられる。尤も、ニュータウンでなくても同じ現象には変わらないのだけど。人が暮らせば、ドラマがあるようにこの小説は50年にわたる、街と人々の物語。希望や挫折の繰り返し。街があるから人が暮らし、そこに新しい価値観も生まれてくる。過去を振り返ると、苦さもこみ上げてくるけれど、もう一踏ん張りしようと下半身に力を込めてみる。2017/11/23