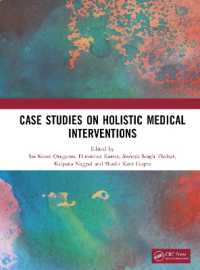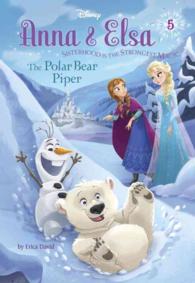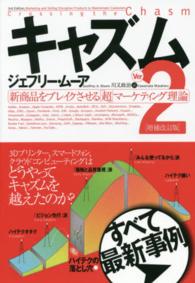内容説明
ファシズムの脅威のなか書き上げられたフロイトの「遺著」。猛威をふるっていた反ユダヤ主義の由来について、フロイトは、モーセはエジプト人だったとする仮説からユダヤ教の成立と歴史を考察し、みずからの精神分析の理論を援用してキリスト教の誕生との関係から読み解く。
目次
第一論文 モーセ、一人のエジプト人
第二論文 もしもモーセがエジプト人であったなら
第三論文 モーセ、その民族、一神教
著者等紹介
フロイト[フロイト] [Freud,Sigmund]
ジークムント・フロイト。1856‐1939。東欧のモラビアにユダヤ商人の長男として生まれる。幼くしてウィーンに移住。開業医として神経症の治療から始め、人間の心にある無意識や幼児の性欲などを発見、精神分析の理論を構築した。1938年、ナチスの迫害を逃れ、ロンドンに亡命。’39年、癌のため死去
中山元[ナカヤマゲン]
1949年生まれ。哲学者、翻訳家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まると
28
モーセがもたらした一神教がいかにして成立し、幾多の苦難を乗り越えて持続できたのかについて論じた、驚くべき考察です。心理学の理論を用いて、モーセ(原父)殺しなどの仮説を大胆に立てている。ユダヤ教から派生したキリスト教が割礼を廃止し、異民族にも受け入れられていく一方で、土俗的な宗教を捨ててキリスト教に帰依したゲルマン民族は、ユダヤ人を暗に恨むようになったとの推論もまた面白い。フロイトはこれをナチスによる迫害が進行し、亡命先で闘病中の最晩年に、遺作として残したわけだが、その思いがどこにあったのかも知りたくなる。2021/12/19
evifrei
19
フロイトの遺書となった三部の論文からなる書籍。第一部・第二部ではモーセがエジプト人であることを仮定した宗教批判が展開され、第三部では反ユダヤ主義とキリスト教の関係が精神分析の理論を援用しながら説かれる。ファシズムの台頭する時代に当時の社会には受け入れられない思想である事を理解しながらも、自身の見解を明らかにするというフロイトの魂の一冊。精神分析という自らの研究分野に対する誠実さと真摯さを体現したといえるのではないか。神経症と原父殺しについて述べたところなどはフロイトらしい見解だ。2020/04/07
魚京童!
16
出エジプトのウィキを読んだ。ヘブライ人(イスラエル人?ユダヤ人?)だから、エジプトから民を率いて、エジプトから出て、海を割った人という定説に対して、実はエジプト人じゃないの?って話。そうするとどうなるのかよくわからなかった。でも思ったのは、アイヒマンのときも、指導者が輸送を助けてたんだよね。これは成功したパターンなだけじゃないの?違うなー。率いたんじゃなくて、唆したって話になるからなんか変な感じになるのか。この辺知識がないからわからないんだよね。2024/06/22
∃.狂茶党
13
宗教的なものに疎いために、フロイトによる宗教の解体は奇妙なものに思える。 父親殺しとその残響。心理学的紐解きはいいとして、民俗学的な考え方について、迂闊すぎないか? パウロによる、キリスト教の成立は、本書で一番納得のいくものだが、『幻想の未来』と、『トーテムとタブー』を読む必要があるっぽい。 で、この本読んでるときに、『家畜人ヤプー』に出てきた、社会システムが浮かんでしょうがなかった。 2023/03/23
イタロー
4
濃い本。 モーセが実はエジプト人であり、エジプト由来の唯一神を掲げ、ユダヤ人と後に呼ばれるようになる民を引き連れエジプトを脱出し、そして民に殺されたのではないか……という仮説から、「ヤハウェの宗教」が「抑圧されたものの回帰」として「モーセの宗教」になってゆくメカニズムを、精神分析の手法で試みた書。 個人心理学と集団心理学、精神分析と宗教の結節点を見出そうとしていてヤバイ。特に第三論文の第二部の途中は読んだことのない感触で頭が痛くなった。第一と第二論文は歴史ミステリー的でわくわく。 おススメ。2024/06/03