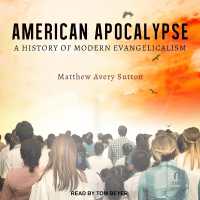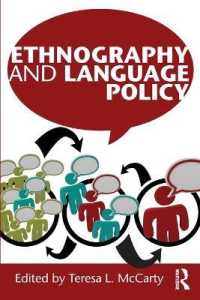内容説明
心ならずも地方連隊勤務となった青年グリニョーフは、要塞の司令官の娘マリヤと出会い、やがて相思相愛になる。しかし父親に反対されるなか、プガチョーフの反乱が起こり、マリヤは囚われ、グリニョーフも捕虜になってしまう…。みずみずしい新訳で甦るプーシキン晩年の傑作。
著者等紹介
プーシキン[プーシキン] [Пушкин,А.С.]
1799‐1837。ロシアの詩人、作家。ロシア近代文学の父と呼ばれるロシアの国民詩人。短詩作品、物語詩、劇詩、韻文小説、散文小説など多くの分野で名作を残す。貴族の家に生まれ、賭博、恋愛、決闘に彩られた奔放な生涯を送り、ついには美貌の妻をめぐり、フランス人将校と決闘の末、37歳で落命。後世の作家たちへ大きな影響を与え、今なおロシア人の魂のよりどころとなっている
坂庭淳史[サカニワアツシ]
早稲田大学教授。ロシア文学者(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ケイ
132
たくさんのロシア名が出てくるも、慣れてくるとまあなんとも楽しや。最初は、主人公の破天荒ぶりとサヴェーリイチの絶望に、彼らのその後を心配したが、まあその若気の至りがとんでもない展開をみせてくれる。フィールディングやセルバンテス作品のような楽しさの底にあるのは、エカテリーナ二世に対するプガチョーフの反乱である。個人的にエカテリーナ二世は好きでないので、余計にプガチョーフに肩入れしてしまった。プーシキン晩年の作品と裏表紙に紹介されているが、彼が亡くなったのは37歳なので作品に力がある(続く)2019/07/02
榊原 香織
125
面白かった。最初は何だこいつ、と思ってたんだけど。短いわりに大河ドラマ。 従者サヴェーリイチがサンチョ・パンサ並みに素晴らしい。 プガチョーフの乱に絡んだ話。2024/11/21
Willie the Wildcat
68
プガチョーフの乱に垣間見る人間模様。人生の荒波に揉まれるピョートルの成長を、2つの軸で計る。1つ目の軸が、サヴェーイリチとのシヴァーブリンという対極。2つ目の軸が、マーシャとプガチョーフという対極。前者の「義」が手段となり、後者が目的の「愛」の在り方を示す。応えるピョートルの言動に垣間見る変化。処刑場でプガチョーフと交わした”会話”。拡大解釈すれば、国家・民衆への親愛を認め合ったのではなかろうか。『省かれた章』の是非は、どらちもアリかな。なお、巻末の年譜で知る著者の最期の迎え方も意味深だなぁ。 2019/07/14
kazi
40
ロシア文学といえば長大・難解・陰鬱のイメージだったのだが、こんな読みやすい作品もあるのね。ある意味講談風というのか、囚われの身の女性を勇敢で一本気な主人公が救出する冒険小説のような明るい作品で、想像以上に分かりやすく面白かった。詩人という印象が強いプーシキンだが、散文でもこんな長編を残していたのか・・。というか、このレベルの文量の長編小説はこれが唯一みたいですね。ドストエフスキーやトルストイのネチネチとしつこい文体も好きだが、簡潔明瞭なプーシキンの散文もこれはこれで結構面白いと思いました。2022/07/02
みつ
34
『大尉の娘』という標題とは異なり、若い将校が語るロマンスかと思いきや、もっぱら舞台は18世紀後半のロマノフ朝帝国を震撼させたプガチョーフの乱が中心。語り手の主人公の若さを強調するためか、語尾が「〜なんだ」となっているのは少々読みづらい。プガチョーフたちの暴虐な振る舞いの中で主人公は処刑されることもなく、そればかりか意外な関係を持つのは不思議といえば不思議。最後の章の後半で語り手を離れ、「大尉の娘」が思いがけぬ人物と出会う。小説としては駆け足の結末だが、ロシア文学特有の冗長さがなく、疾走感に満ちて一気読み。2024/02/23
-
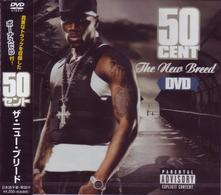
- DVD
- 50セント/ザ・ニュー・ブリード