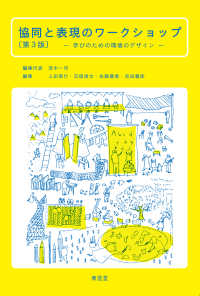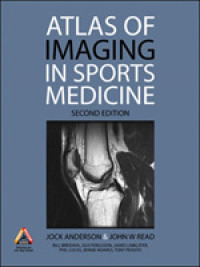内容説明
3巻の「図式論」と「原則論」では、カテゴリーの根拠づけが対象にたいしてどのように機能するのか、それと時間がどのように関係するのかが解明される。イギリス経験論(ヒューム)を根本的に批判し、認識の主体と対象の相互の関係を論じた観念論も批判する。
目次
第1部 超越論的な原理論(超越論的な論理学(超越論的な分析論(原則の分析論(超越論的な判断力一般について;純粋な知性の概念の図式論について;純粋な知性のすべての原則の体系;すべての対象一般を感覚的な存在と叡智的な存在に区別する根拠について;知性の経験的な使用と超越論的な使用の混同によって生まれる反省概念の両義性について))))
著者等紹介
カント,イマヌエル[カント,イマヌエル][Kant,Immanuel]
1724‐1804。ドイツ(東プロイセン)の哲学者。近代に最も大きな影響を与えた人物の一人。『純粋理性批判』『実践理性批判』『判断力批判』のいわゆる三批判書を発表し、批判哲学を提唱して、認識論における「コペルニクス的転回」を促した。フィヒテ、シェリング、ヘーゲルとつながるドイツ観念論の土台を築いた
中山元[ナカヤマゲン]
1949年生まれ。哲学者、翻訳家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェルナーの日記
232
第3巻は第2巻の続きで、『原則論』と『図式論』について考察。”困難は分割せよ”との諺とおり、分析論に図式論を組み込んだ形になっている。そして本巻において『超越的な判断力』の項を設け、対象を正しく(カントは正しいという言葉は使用しておらず、混じりっ気のない純粋なものとしている)判断するために『純粋理性批判』の原則を詳細に根拠づけをする。アプリオリな直観は感性として自己完結するが、直観を理解するものとして概念の必要性から知性を組み込んだ。その中で、最大の問題としているのが『時間と空間』についてである。 2021/12/20
1.3manen
49
この巻は解説のみに依存。。判断力はすでに定められた規則や原理に、個別の判断が正しくしたがっているかどうかを判断する能力、与えられた規則に基づいて個々の事例を判断する能力(342頁~)。これだけみると、いかにも、公務員の判断を書いてあるような冷徹さが感じられる(汗)。別の『判断力批判』で、判断力には、規定的な判断力と反省的な判断力が存在するという(357頁)。後者の判断なくして、PDCAサイクルは回らないな、今風にいうと。。2022/07/27
かわうそ
43
感性と知性は異質なものです。異質なものは第3のものを想定しなければ結びつけることが出来ないのです。ゆえに概念を感性化すること、直観を概念化することが必要になります。第3なものに必要不可なものとしてカントは2つの条件があるとします。1つ目は像のような具体性をもつことと、カテゴリーのように純粋なものを持っていることです。2つ目は感性的なものと知性的なものをもっているべきだということです。この2つの条件を満たせるのは図式であり、空間だとカントはいいます。時間によって図式によって感性と知性は結び付けられるのです。2023/01/01
ころこ
41
前半の図式論のところで「犬」を例示して言語論に入りそうになっているところで唸ります。言語哲学はカント以降20世紀に入ってからですが、着眼点の鋭さを見せるのは流石です。本書はいわば汎用AIについて構想していることに近いですが、現在のAIでも記号接地問題といって、言語が何を規定しているのか我々は未だに解明していません。カントもカテゴリーについて色々と考えてきたものの、それらが何によって規定されているのか、言語表象による曖昧さに気付かざるを得なかったのでしょう。2022/04/29
かわうそ
37
『カテゴリーとはそもそも思考の形式にほかならないのであり、直観において与えられた多様なものを、意識においてアプリオリに結合するための論理的な能力をそなえているだけである。そしてわたしたちには、感性による直観しか可能でないのであり、これをカテゴリーから取りのぞいてしまうと、わたしたちには少なくとも客体を与えてくれる【空間と時間という】感性の純粋な形式ほどの意義もなくなるのである。』238 つまりは知性は制限されるのである。知性と感性が結びついてはじめて認識や経験が可能になる。 2024/09/25