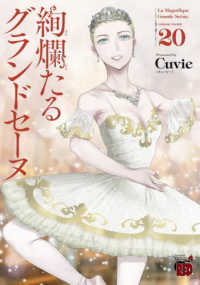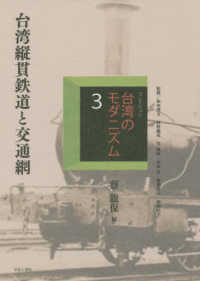内容説明
中年のしがない下級役人マカールと、天涯孤独な娘ワルワーラ。二人は毎日手紙で励ましあい、貧しさに耐えている。互いの存在だけを頼りに社会の最底辺で必死に生きる二人に、ある日人生の大きな岐路が訪れる…。後のドストエフスキー文学のすべての萌芽がここにある。著者24歳のデビュー作、鮮烈な新訳。
著者等紹介
ドストエフスキー,フョードル・ミハイロヴィチ[ドストエフスキー,フョードルミハイロヴィチ][Достоевский,Ф.М.]
1821‐1881。ロシア帝政末期の作家。60年の生涯のうち、巨大な作品群を残した。ニヒリズム、無神論との葛藤を経て、キリストを理想とした全一的世界観の獲得に至る。日本を含む世界の文学に、空前絶後の影響を与えた
安岡治子[ヤスオカハルコ]
1956年生まれ。東京大学大学院教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
-





への六本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
藤月はな(灯れ松明の火)
111
テンション高い系の市井の人々が唾飛ばしながら語りかけてくるドストエフスキーの処女作。読んでみて余りの昏さに絶句。社会の最底辺でもがきながらも互いを手紙で励まし合う親子のような二人。しかし、相手に相応しい人間になろう、助けたいと思い、無理に背伸びし、借金するマカールを周囲は嘲笑い、マカールの援助がワルワーラの自尊心を削っていく。この、貧しさや頑張る人に対する人々の物見高く、冷ややかな視線と憐憫の苦さ、何もかも無にするか、金を得るかを無情に迫る社会は変わったのか。否。それが読後をより一層、重苦しくさせている。2018/10/28
読特
80
九等官とは行き止まりの等級。清書係がそれ以上出世することはない。お相手は20歳前後の孤独な少女。書簡が往復する舞台は19世紀前半の帝政ロシア。ソ連となる半世紀以上も前。「うだつが上がらぬ中年下級官吏と薄幸の若い娘の恋物語」…そんな構図だけで語れぬ何かがある。迎える結末はそれしかないだろうという運命。”貧しさ”とはそういうものかと諦観する。1845年発表の処女作。グイグイ引き込まれるのは、後期長編に同じ。隠し秘めたる普遍の機微を突く。心の奥底にある闇深きもの。気づかされたその存在にふと魅了されている。2022/08/29
星落秋風五丈原
63
だいたい若い作家のデビュー作というのは、自分の年齢相応の人物(だいたい自分の性格に補正が入ってる)や架空キャラは書けるが、年齢が上の人物については想像の域を出ないので、どうしても“作った”感が出てしまう。だから24歳のドストエフスキーが、人生も半ばに差しかかった48歳ジェーヴシキンの悲哀を描けたというのは素晴らしいことだ。結局は富裕なブイコフとの結婚を択ぶワルワーラの方が、よほど人生を達観している。切ない悲恋を最初に書いてしまったら、後に続く恋愛に幸せなものがあるのだろうか?2022/10/30
kazi
63
読みました。大文豪ドストエフスキーが華々しく文壇デビューを果たした「貧しき人々」。雑誌編集者ネクラーソフと著名な批評家であったベリンスキーは今作を読んで「新しいゴーゴリが現れた」と大絶賛したそうです。デビュー作から凄いな~(^▽^;) 物語は初老の小役人マーカルとみなしごの少女ワーレンカの往復書簡という形式になっており、お互いが身の回りで起こった出来事を連絡しあう形で話が進みます。2021/01/06
著者の生き様を学ぶ庵さん
52
ドストエフスキーのデビュー作。老人とお嬢さんの往復書簡形式のロシア式貧乏小説。いかにもロシアらしい重苦しさが2人の貧乏生活を通して伝わってくる。2人の間は、極度の貧乏と大袈裟に相手を思いやる純愛と回りくどい手紙で埋め尽くされているが、最後に貧乏なお嬢さんは下衆な小金持ちに求婚され、貧乏生活から脱出するとともに物欲を身に纏う。24歳にしていかにもロシア的な作品を発表したドストエフスキーは、20代で既に文豪の片鱗を感じさせる。重々しいなあ、ロシア小説は。たまには良いが、どっぷり浸かると普段の世界に帰れない。2016/09/13
-
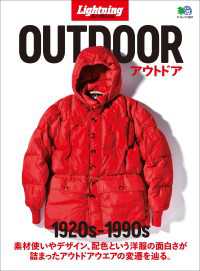
- 電子書籍
- Lightning Archives …
-
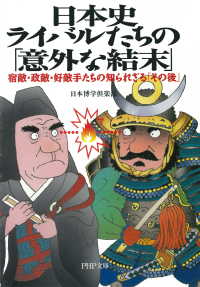
- 電子書籍
- 日本史・ライバルたちの「意外な結末」 …