内容説明
ニーチェが目指したのは、たんに道徳的な善と悪の概念を転倒することではなく、西洋文明の根本的な価値観を転倒すること、近代哲学批判だけではなく、学問もまた「一つの形而上学的な信仰に依拠している」として批判することだった。ニーチェがいま、はじめて理解できる決定訳。
目次
第一論文 「善と悪」と「良いと悪い」
第二論文 「罪」「疚しい良心」およびこれに関連したその他の問題
第三論文 禁欲の理想の意味するもの
著者等紹介
ニーチェ,フリードリヒ[ニーチェ,フリードリヒ][Nietzsche,Friedrich]
1844‐1900。ドイツの哲学者。プロイセンで、プロテスタントの牧師の家に生まれる。ボン大学神学部に入学するが、古典文献学研究に転向。25歳の若さでバーゼル大学から招聘され、翌年正教授に。ヴァーグナーに心酔し処女作『悲劇の誕生』を刊行したが、その後決裂。西洋哲学の伝統とキリスト教道徳、近代文明を激烈に批判、近代哲学の克服から現代哲学への扉を開いた。晩年は精神錯乱に陥り1900年、55歳で死去
中山元[ナカヤマゲン]
1949年生まれ。哲学者、翻訳家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Aster
72
最後の論文はかなり共感出来る。思考の枠組みがもうそうなってしまっているのだから、言葉で表すことも危ういと。宗教、特にキリスト教は人類を治癒するような役割で持って登場した訳だが、全て裏目に出ている。歴史を、系譜を辿ることの重要性が分かった。ニーチェ入門書で得た知識が全て刷新された。ニーチェは絶対に入門で済ませるような哲学者じゃない。(まぁ全員そうなのですが…敢えて強調して言いたくなりました)2021/01/12
syaori
56
「人間はどのような条件のもとで、善いとか悪いとかの価値判断を」考えだしたのか、それが人間にもたらしたものは何かを辿ることで見えてくるのは、「習俗の狭苦しさと規則のうちに閉じ込められ」発散することができなくなった生の本質、自発的で攻撃的で祝祭的なそれを内に向け自らを痛めつける人間の姿。負い目、原罪を作り出して「幸福になる権利を疑」うようになるほどに転倒した世界の姿。この「腐敗した現代」を糾弾するニーチェの声が高く強く響くのは、自分もまた転倒した世界で「虚無を意欲」しているからなのかもしれないと感じました。2019/02/27
かんやん
27
善と悪、罪、疾しい良心、禁欲の理想などの概念の発生を歴史的に考察する、系譜学というほどには学術的ではなく、罵詈雑言を繰り返すいつものニーチェだけど、ユダヤ的ルサンチマンが価値転倒して道徳を捏造する過程は、彼の憎悪・嫌悪・吐き気を共有する者ではない自分にも息を呑むような迫力があった。二千年のキリスト教・道徳・ルサンチマン相手に孤軍奮闘するから、ますます芝居がかって言葉も痛烈に。まるで預言者だ。荒野で叫ぶ者だ。その叫びは遠く現代の日本に暮らす微温的なおっさんの耳にもしかと届いたのであった。2018/03/24
かわうそ
26
岩波文庫版と同時に読み進めているがこちらの訳の方が遥かに理解しやすい。司祭が生を諦めてるように見せかけて実は最も生に執着しているというのは確かに。人間は苦痛を受け入れられる。むしろ、苦痛を望む場合もあるのだが、苦痛を受け入れる意味がないと簡単に壊れる。コペルニクス以降、人間は動物に成り下がり、人間の自己卑下の時代が始まったといえよう。それまであった神に最も近い存在としての自覚が打ち壊されたのである。それによって苦痛の意味が理解できなくなったのが人間の無気力の始まりであったのかもしれない。2022/07/07
ころこ
26
第二論文の前半は、道徳的人間像を近代的人間像と読み替えれば、フーコーとほぼ同じことが読み込めます。「負い目」という道徳の主要な概念が、極めて即物的な概念である「負債」から生まれるとしています。直ぐに思い出すのが、『ヴェニスの商人』で負債の額に相当する身体を差し出すやり取りがガチだったということです。「痛み」に対する道徳的内面が痛みの強度を決めているというように、本論から現代の資本主義社会における負債論が可能ならば、道徳的な「負い目」を忘却しない身体が「負債」を成立させているというようにみえるのですが。2018/07/18
-
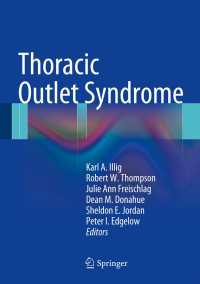
- 洋書電子書籍
- Thoracic Outlet Syn…
-

- 電子書籍
- 憲法学の病(新潮新書) 新潮新書






