内容説明
1968年1月、南ベトナム解放戦線による一斉攻撃を受けて、サイゴン(現ホーチミン)の街は様相を変える。いつどこからロケット弾が飛んでくるか知れない厳戒態勢の街に筆者は赴いた。なぜ、対立し戦うのか、正義はどこにあるのか。鋭利な眼が探る―。捉えたものは、ただ墓標が増え続けること。それだけが、「真実」だった。戦禍を克明に伝え残す異色のルポ。
目次
1968(サイゴンの裸者と死者;ジャングルの躓ける神;“みんな最後に死ぬ”;十字架と三面記事)
1973(蒸暑い死;影なき災禍;最後の撤兵―勝者もなく、敗者もなく;聖者来たりなば―ココナツ坊主会見記;ブーゲンヴィリアの木の下に;サイゴン・一つの時代が終った;荒野の青い道;十字架の影射すところ;不安な休憩)
著者等紹介
開高健[カイコウタケシ]
1930年大阪市生まれ。大阪市立大卒。’58年「裸の王様」で芥川賞を受賞して以来、次々に話題作を発表。ベトナム戦争のさなか、しばしば戦場に赴いた経験は、『輝ける闇』(毎日出版文化賞受賞)、『夏の闇』などに凝縮され、高い評価を受けた。’79年『玉、砕ける』で川端康成文学賞、’81年一連のルポルタージュ文学により菊池寛賞、’87年、自伝的長編『耳の物語』で日本文学大賞など、受賞多数。’89年逝去。享年58(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
イロハニ
18
著者が三度訪越した際の68年2回目と73年3回目のルポだが作中で初回65年の回顧もある。北の攻勢により大発生する夥しい南への人間流出果たして人民解放とは何なのか?いずれ人々の逃げ場は海しか無くなるのかと危惧する。73年3月29日…星条旗を巻く(furlする)小さな式の後、米軍撤退完了。本書がルポからの事実取材より作者の考察が勝っている印象を受けたのは残念だ、各所に有る南国の日射や花の描写がかすみがちだ。だが本書は散文的且つ詳細な年表と併読した時にベトナム戦争の巨大な災禍のパズル画の価値ある一片となる筈だ。2023/04/18
ちゃーびん
7
前半は開高氏が真面目に報道取り組もうとしているのか、かなり読みづらいものだった。単純に分かりづらく、語学もずいぶん不得意なのか、カタカナのベトナム語もかなりいい加減で表記も不規則、翻訳や言い回しも不自然で、雑さに驚かされます。きちんとしたレポート的な報道は正確さや読みやすさにおいてもベトナム報道の本多勝一氏の足元にも及ばない印象。こういうのぜんぜん向いてない方ですね。 変わって後半は自由演技的に自身で見たものを感じたままに書いている事が多くなりとても読みやすく、記録資料としても面白かったです。2024/02/10
さっと
7
ベトコンに急襲されて九死に一生を得たのちの二度のベトナム行きの記録。1964年-65年のその体験は『ベトナム戦記』に収められておりアメリカの軍事派遣が本格的になる前、1968年は解放戦線が南へ浸透し緊張感が一気に高まる、1973年は和平調停でアメリカ兵もめったに見ることができなくなるほど戦地は様変わりしていく。こうしてみると小説家はベトナム戦争の潮流の節目に立ち会っていたわけだが、三面記事や噂の反応や転向や信仰の村や自称専門家エトセトラエトセトラあくまでもミクロな視点に貫かれている。2020/10/20
モリータ
6
前から読みたかった本2015/05/13
hirayama46
5
ベトナム戦争について知りたくて読んだのですが、本書は主に1968年と73年に書かれた文章をまとめたものなので、あくまでも渦中であり、なおかつ当時の人にとっては知っていて当然のことまでは説明されていないので、何も知らないまっさらな状態で読むにはちょっと難しかったかな……という感触。現地での叙景的な描写は楽しめましたが、指導者たちの政治的な偏向などについては理解がおぼつきませんでした。2021/08/09
-
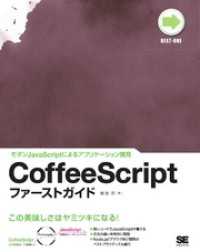
- 電子書籍
- CoffeeScriptファーストガイド




