出版社内容情報
人文学の論文執筆には、基礎となる習得必須の知識と技術がある。しかし、それを現在の大学教育はうまくカリキュラム化できていない。どんな条件を満たせば論文は成立したことになるのか、どの段階でどの程度の達成が要求されるのか、そしてそのためにはどのようなトレーニングが必要なのか。そもそも、なんのために人文学の論文は書かれるのか。期末レポートからトップジャーナルまで、「独学で書く」ためのすべてを網羅する。
内容説明
人文学の論文執筆には、基礎となる習得必須の知識と技術がある。しかし、それを現在の大学教育はうまくカリキュラム化できていない。どんな条件を満たせば論文は成立したことになるのか、どの段階でどの程度の達成が要求されるのか、そしてそのためにはどのようなトレーニングが必要なのか。そもそも、なんのために人文学の論文は書かれるのか。期末レポートからトップジャーナルまで、「独学で書く」ためのすべてを網羅する。類書の追随をまったく許さない、アカデミック・ライティング本の新定番。
目次
原理編(アーギュメントをつくる;アカデミックな価値をつくる;パラグラフをつくる)
実践編(パラグラフを解析する;長いパラグラフをつくる;先行研究を引用する;イントロダクションにすべてを書く;結論する)
発展編(研究と世界をつなぐ;研究と人生をつなぐ)
演習編
著者等紹介
阿部幸大[アベコウダイ]
1987年、北海道うまれ。筑波大学人文社会系助教。専門は日米文化史。2023年に博士号取得(PhD in Comparative Literature)。研究コンサルティングのベンチャー、アルス・アカデミカ代表(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
シリウスへ行きたい
1.3manen
エジー@中小企業診断士
Carlyuke
ife
-
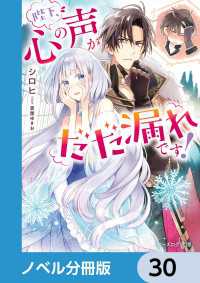
- 電子書籍
- 陛下、心の声がだだ漏れです!【ノベル分…




