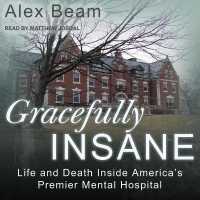出版社内容情報
「この草子、目に見え心に思ふ事を」。栄華を誇った中宮定子を支えた女房・清少納言は、なぜ膨大な言葉を書き残さなければいけなかったのか……。痛快な批評が笑いや哀感と同居する、平安朝文学を代表する随筆。ユニークな視点と鋭く繊細なまなざしですくい取った世界観を、歯切れ良く瑞々しい新訳で。「ここにもあった、いとをかし」。解説、年譜のほかに、位階、装束、牛車、建物などの図版資料を含む、宮廷生活ガイド付き。
内容説明
「この草子、目に見え心に思ふ事を」。栄華を誇った中宮定子を支えた女房・清少納言は、なぜ膨大な言葉を書き残さなければいけなかったのか…。痛快な批評が笑いや哀感と同居する、平安朝文学を代表する随筆。鋭く繊細なまなざしですくい取った世界観を、歯切れ良く瑞々しい新訳で。
目次
春はあけぼの
ころは
正月一日は
同じことなれども
思はむ子を
大進生昌が家に
上に候ふ御猫は
正月一日、三月三日は
よろこび奏するこそ
今内裏の東をば
山は
市は
峰は
原は
淵は
海は
みささぎは
わたりは
たちは
家は〔ほか〕
著者等紹介
清少納言[セイショウナゴン]
生没年未詳。平安時代中期の女性文学者。本名は未詳。父の清原元輔、曽祖父の深養父はともに歌人。橘則光と結婚するがまもなく離別し、その後、藤原棟世と再婚。993年(正暦4)ごろから一条天皇の中宮定子に出仕した。和漢の才に秀で、寵を受けた。晩年は「月の輪」なる地に隠棲したと伝わる。著作に随筆『枕草子』、家集『清少納言集』などがある
佐々木和歌子[ササキワカコ]
1972年、青森県生まれ。文筆家。東京大学大学院人文社会系研究科修士課程修了。専門は日本語日本文学。(株)ジェイアール東海エージェンシーで歴史文化系コンテンツの企画制作に携わりながら、古典文学の世界をやさしく解き明かす著作を重ねる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
えつ
真琴
amanon
いるか
葉菜枝
-
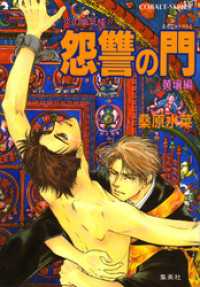
- 電子書籍
- 炎の蜃気楼27 怨讐の門(黄壤編) 集…