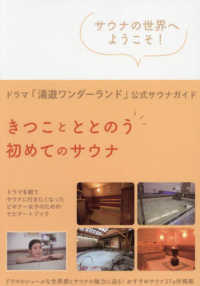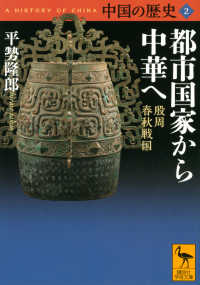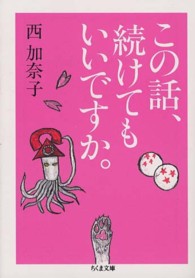内容説明
カブール陥落から2年―タリバン統治の実態は?女性の権利は?日本が果たすべき役割は?激変するアフガニスタン社会を、第一人者が広く深くリポート。
目次
第1章 アフガニスタン和平実現に向けた取り組み
第2章 ターリバーン暫定政権による統治
第3章 「自由と独立」を求める反ターリバーン運動
第4章 激変する社会 対談:安井浩美×青木健太
第5章 国外退避する人々
第6章 陸封国の対外関係と日本が果たすべき役割
終章 自己の模索への旅
著者等紹介
青木健太[アオキケンタ]
1979年東京生まれ。公益財団法人中東調査会研究主幹。上智大学卒業。英ブラッドフォード大学大学院平和学修士課程修了(平和学修士)。専門は現代アフガニスタン・イラン政治。2005年から国連開発計画・アフガニスタン政府省庁合同事業アドバイザー、在アフガニスタン日本国大使館書記官などとして同国で約7年間勤務。帰国後、外務省国際情報統括官組織専門分析員、お茶の水女子大学講師を経て現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
71
岩波新書『タリバン台頭』の著者によるアフガニスタン情勢の概説書。現地生活が長く、食文化などについてもコラムで取り上げていて、本来のアフガニスタンの豊かさも垣間見ることができる。また現地在住の日本人特派員とのZOOMによる対談や、イランに避難しているタジク系の難民へのインタビューなどもあり、リアルな様相を見せてくれる。50年に及ぶ戦乱のうち、現在の混乱をもたらしたのが2001年に侵攻し、かき回したあげくさっさと手を引いたアメリカにあるのは明らか。ガニー大統領の国外脱出がターリバーン台頭をもたらした。良書。2023/10/23
かんがく
14
ウクライナ情勢に比べると報道される頻度も少ない、ターリバーン支配後のアフガニスタン情勢についての詳細なレポート。特に現地に住む日本人記者との対談、イランに逃れた難民へのインタビューの章が印象に残った。2023/10/10
お抹茶
2
手っ取り早く情報を仕入れられる。1973年の無血クーデターでアフガニスタンの約50年間の戦争と混乱が始まり,ザーヒル・シャー国王の治世下で民主化や女性の参政権が進み貧しいながらも安定していた時代は終わった。イスラーム共和国政権に排除されてきたターリバーンに権力を分与するインセンティブは低く,和平プロセスの進展を著しく困難にしている。パシュトゥーン民族主義も特徴。ターリバーンと反対派の主張は譲歩の余地がなく,言葉では相手を理解させられない状況。アフガニスタンの根本的な問題は教育不足で,国の統治能力がない。2025/06/27
Ahmad Hideaki Todoroki
0
ターリバーン復権後のアフガニスタンを知るには最適の一冊。コンパクトにわかりやすくまとまっています。政治や人権状況以外にも、食事や言語などについてもコラムで触れられています。とは言え、アフガニスタン人の本音はこの本だけではわからない。誰がターリバーンを支持しているのか、何故話し合いが不調に終わるのか、疑問は幾つも湧いてくる。ガニ政権自壊は、平和構築学や開発経済学の敗北でもあるので、それらの専門家の分析と反省を読みたいと思う。2024/09/10
よしおか のぼる
0
特にここ2年くらいのアフガニスタンの実情の素描。2023/08/03
-

- 洋書電子書籍
- リモートセンシングの物理学・技法入門(…