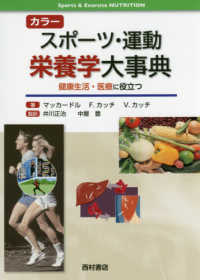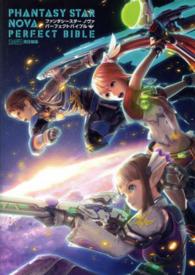内容説明
肉じゃが?ポテサラ?オムライス?「おふくろの味」の正体とは―?無性に食べたくなる時もあれば、揉め事の火種にもなる。誰もが一度は聞いたことがあるのに正体不明の「味」の謎―。
目次
第1章 「おふくろ」をめぐる三つの謎(「おふくろ」という言葉はどこから来たのか?;「おふくろ」と言っているのは誰なのか? ほか)
第2章 都市がおふくろの味を発見する―味覚を通じた「場所」への愛着(地名食堂の系譜;東京昭和の「おふくろ」たち ほか)
第3章 農村がおふくろの味を再編する―「場所性」をつなぎとめる味という資源(変化する農山漁村;「おふくろの味」の再編―没場所性とのせめぎ合い ほか)
第4章 家族がおふくろの味に囚われる―「幻想家族」の食卓と味の神話(家族と食事の変遷;新たな食経験と故郷の変化のはざまで生まれる幻想 ほか)
第5章 メディアがおふくろの味を撹乱する―「おふくろの味」という時空(一九七〇年代まで―「おふくろの味」のつくり方;一九八〇年代―百花繚乱の食の楽しみと苦しみ ほか)
著者等紹介
湯澤規子[ユザワノリコ]
1974年、大阪府生まれ。法政大学人間環境学部教授。筑波大学大学院歴史・人類学研究科単位取得満期退学。博士(文学)。専門は歴史地理学、農村社会学、地域経済学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
はっせー
68
ご飯を食べるのが好きな人や地方から東京へ上京した人にぜひ読んで欲しい本になっている!「おふくろの味」。最近その言葉さえ聞かなくなっていますよね。ジェンダーの問題からだと思います。本書は「おふくろの味」が誰がつくりどう広まり、どのような味が「おふくろの味」なのかを研究した内容になっている。「おふくろの味」自体がここ40年から50年しか歴史がなくそしてその味に振り回されていることがしれた。味についての研究などはやっぱり面白い。これからもこのような本を読みたい!2024/02/11
おかむら
35
実は肉じゃがは好きじゃなくて、なんかあのジャガイモを醤油うすら甘味で煮るっていうのが嫌いでねぇ、イモは塩で食べたい派なのですが、そんな私でも結婚当初は何回か作ったことある肉じゃが。男の人はみんなおふくろの味が好きっていう思い込みもあったのねー。若かった。ってか夫はほんとに肉じゃが好きみたいで食べたい時は自分で作ってますね今は。本書はおふくろの味の発生から衰退までの40年間(意外と短い歴史…)を解説。最近手料理に飽きてきてるのでウンウン頷きながら読んだ。2023/03/10
タルシル📖ヨムノスキー
26
私の中で「おふくろの味」とはいわゆる味付けのことではなくて、郷土料理とか他の人は使わないであろう特徴的な材料が入った料理が浮かぶ。例えば肉の代わりに魚肉ソーセージの入ったカレーとか。この本では「おふくろの味」という言葉が何時ごろ誕生して、その意味合いが時代とともにどう変化していったかが、たくさんの資料を元に語られる。これによると実は料理が母親や妻の仕事になったのは戦後。そして言葉としての「おふくろの味」が登場するのは高度経済成長期の頃だとか。男性だけでなく実は女性もこの言葉に縛られているという話に納得。2023/11/21
塩崎ツトム
24
本書内ではそんなに酷評している概念ではないけど、「おふくろの味」は高度経済成長期に、労働力としての男が故郷というへその緒から切り離された結果渇望するようになった、パターナリズムとマザコン気質が産んだような感じなんだよな。そのいびつさが特に1980年代後半のバブル期に噴出したという。でも本書前半の「郷土の味」が一種の地場産業化される過程は興味深い。2024/03/12
くさてる
23
「なぜその味は男性にとってはノスタルジーになり、女性にとっては恋や喧嘩の導火線となるのか」という紹介文が面白かった。たしかに「おふくろの味」ってなんだろう。男性が家庭に求める味、ということでわたしも連想した「美味しんぼ」のエピソードも紹介されてて納得。作り手が女性、母親に限定されていた時代からもっと自由なものへと変化していく家庭料理への希望を語った最終章まで、とても面白く読みました。2023/05/14
-
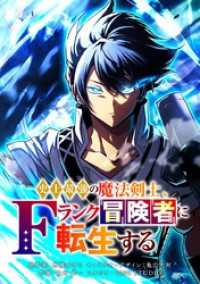
- 電子書籍
- 史上最強の魔法剣士、Fランク冒険者に転…