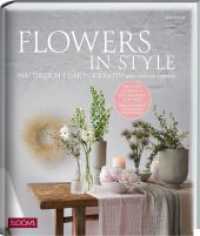出版社内容情報
ザ・ドリフターズや萩本欽一から、ビートたけしを経て、とんねるず、ダウンタウン…と各世代のポイントなる芸人を群像劇として活写する。
内容説明
「売れた」芸人たちの栄枯盛衰の物語。「世代」で読みとくもう一つの戦後史。
目次
第1章 第一世代―いかりや長介と欽ちゃんが「テレビ芸」を作った
第2章 第二世代―「団塊世代」のたけし、「シラケ世代」のさんま
第3章 第三世代―「新人類」としてのとんねるず、ダウンタウン
第4章 第四世代・第五世代―スター不在の群雄割拠時代
第5章 第六世代―テレビへの憧れと挫折
第6章 第七世代―デジタルネイティブ世代が新時代を作る
著者等紹介
ラリー遠田[ラリートオダ]
1979年生まれ。東京大学文学部卒業。専攻は哲学。テレビ番組制作会社勤務を経て、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など、多岐にわたる活動を展開(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きみたけ
67
お笑いの「世代」感がスッキリしました。著者は元テレビ番組制作会社社員でお笑い評論家のラリー遠田氏。各世代のまとめは以下の通り。第一世代:いかりや長介・萩本欽一、「テレビ芸」の発明者。第二世代:ビートたけし・明石家さんま、プロの芸人によるプロの技術。第三世代:とんねるず・ダウンタウン、師弟制度からの解放。第四・第五世代:ナイナイ・ロンブー、スタッフ主導型バラエティ番組時代。第六世代:キングコング・オリラジ、テレビへの憧れと挫折。第七世代:霜降り明星・EXIT、芸人の価値観が多様化したデジタルネイティブ世代。2022/09/17
ma-bo
60
お笑い評論家のラリー遠田さんがお笑いの第1~第7世代を世代別に区切って解説。テレビ世代の私としては、第1がドリフターズ・欽ちゃん、第2が明石家さんま、ビートたけし等、第3はダウンタウン、ウッチャンナンチャン、とんねるず、第4はナイティナイン、爆笑問題あたりはよくわかる。 最近話題になっているので、霜降り明星・EXITあたりが第7世代というのもOK。第5・6世代あたりが一番曖昧なのかな。この世代が曖昧なのは、第2~4世代が今でも活躍していること、テレビ以外に活躍の場を求める様になった事もあるのだろう。2021/05/22
ホークス
45
2021年刊。著者は1979年生まれと若いが、第一世代(いかりや長介や萩本欽一)以降の各世代の芸人、及び時代背景の分析が面白い。ブレイクした人は発明や発見をした人で、気づきや動機は環境とつながっている。貧困などの負のバイアス、裏返しの愛着や理想が新しい笑いを生む。よく知らない芸人も含め、改めて時系列で知る事ができた。どの芸人も浮き沈みがあり、その姿も興味深い。私は最近、賞レースの決勝が楽しい。ハラスメントなネタが減って清々している。本書はテレビ中心の批評。メディア横断のも読みたいけど、理解できる自信は無い2022/05/12
gtn
34
霜降り明星せいやが何気なく使い出し、日常語となった「お笑い第七世代」という言葉を踏まえ、第一世代から年代別に分類し、考証する著者。初めてテレビを主戦場にすることに成功した第一世代のドリフや欽ちゃん、テレビ至上主義の第二世代さんま、制約の多いテレビに固執しない第六、第七世代等、その分析に同感。吉本天然素材が活躍していた頃、芸人がアイドル化し、一切ギャグをいわず、努めて普通のコメントをする若手芸人が確かにいた。それが苦々しかったことを久しぶりに思い出す。2021/07/25
アナクマ
32
テレビを軸にすえて滑らかに語る世代論。世代区分と取り上げた芸人の選択にも納得(基準は生年と、早期に頭角を表したこと)◉各期の特質/武器/時代の空気感 →TV芸の発見(第一)、闊達な適応と発展(第二)、権威の否定(第三)、涙を見せ、立ち回り、それぞれの城(第四・五)、臨機応変な戦略と新市場の開拓(第六、例外は千鳥)、自然な多様化受容と洗練(第七)◉楽しく読みながらも、時代の合せ鏡である彼らのサクセス・ストーリーからは、我が身をふりかえり学ぶ点も多くあり。器用であれ不器用であれ、共通点は〈熱と努力〉かと。2023/05/21
-
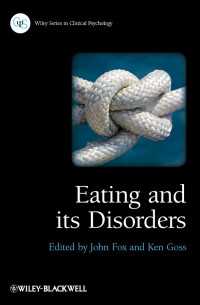
- 洋書電子書籍
-
摂食障害
Eating and …