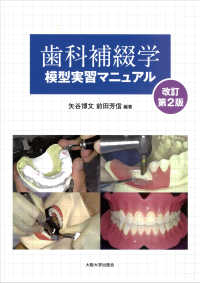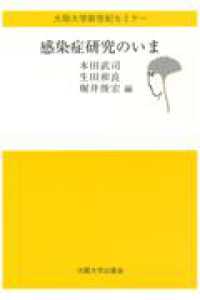出版社内容情報
※2020年8月21日(金)に開催したオンラインイベントのアーカイブ配信です。
「愛読書は古典です」と言える人になる…!
紀伊國屋書店新宿本店と光文社古典新訳文庫がコラボした大人気イベントが、1冊の本になりました。古典文学好きの方はもちろん、敷居が高いと感じている方も、この機会にぜひ、文学への扉を叩いてみませんか。
内容説明
混迷の深まる現代に、何らかの指針を求めつつ、現実世界をひたむきに生きる人々にとって、文学は「即効性のない教養」として、魅力的、かつ有用な存在ではないだろうか。登場人物も作者も、じつは私たちと同じような世界に生きていた「隣人」。とはいえ、古典文学は、なぜかいまだに敷居の高いジャンルと思われていることも事実だ。新訳シリーズとして人気の「光文社古典新訳文庫」を立ち上げた駒井稔が、その道の専門家である翻訳者たち十四人に、初歩的なことから果敢に話を聞いた。肩の力を抜いて扉を開け、名翻訳者たちの語りを聞くうちに、しだいに奥深くまで分け入っていく…。紀伊國屋書店新宿本店で続く大人気イベントを書籍化。イベントのもっとも刺激的で濃厚な部分を再現する。
目次
フランス文学の扉(プレヴォ『マノン・レスコー』 自由を求め、瞬間に賭ける―フランス恋愛小説のオリジン;ロブ=グリエ『消しゴム』 戦争体験に裏打ちされた、ヌーヴォー・ロマンの方法論 ほか)
ドイツ文学の扉(トーマス・マン『ヴェネツィアに死す』『だまされた女/すげかえられた首』 謹厳な作家が描くエロスの世界・三部作;ショーペンハウアー『幸福について』 天才哲学者の晩年のエッセイはなぜベストセラーになったのか?)
英米文学の扉(デフォー『ロビンソン・クルーソー』 百カ国以上で訳された「イギリス最初の小説」の持つ魅力;オルダス・ハクスリー『はずらしい新世界』 『一九八四年』と並ぶ、元祖「ディストピア小説」を読み解く ほか)
ロシア文学の扉(ナボコフ『カメラ・オブスクーラ』『絶望』 『ロリータ』の作家が、亡命時代にロシア語で書いた小説の謎;ドストエフスキー『賭博者』 文豪の三つの病、そしてルーレットと性愛と創作の関係とは?)
日本文学・アフリカ文学・ギリシア哲学の扉(鴨長明『方丈記』 達観していない作者、災害の記録―予想外の人間臭さの魅力;アチェベ『崩れゆく絆』 世界的ベストセラーに見る、アフリカ社会の近代との出会い ほか)
著者等紹介
駒井稔[コマイミノル]
1956年横浜生まれ。慶應義塾大学文学部卒。’79年光文社入社。広告部勤務を経て、’81年「週刊宝石」創刊に参加。ニュースから連載物まで、さまざまなジャンルの記事を担当する。’97年に翻訳編集部に異動。2004年に編集長。2年の準備期間を経て’06年9月に古典新訳文庫を創刊。10年にわたり編集長を務めた。現在、ひとり出版社を設立準備中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
藤月はな(灯れ松明の火)
kaoru
燃えつきた棒
molysk
yutaro13
-
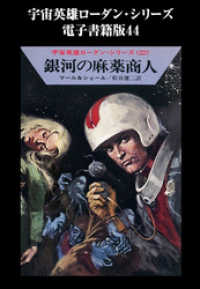
- 電子書籍
- 宇宙英雄ローダン・シリーズ 電子書籍版…
-
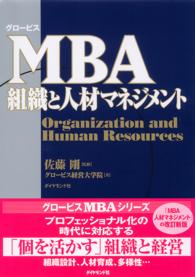
- 電子書籍
- MBA組織と人材マネジメント