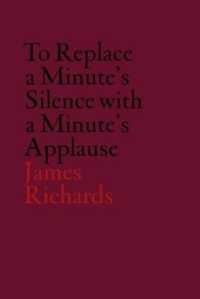内容説明
「帝王切開なんかしたら落ち着きのない子に育つ」「赤ちゃんには母乳が一番。愛情たっぷりで頭もよくなる」「3歳までは母親がつきっきりで子育てすべき。子もそれを求めてる」出産や子育ては、このようなエビデンス(科学的根拠)を一切無視した「思い込み」が幅をきかせている。その思い込みに基づく「助言」や「指導」をしてくれる人もいる。親身になってくれる人はありがたい。独特の説得力もあるだろう。しかし、間違っていることを、あなたやその家族が取り入れる必要はまったくない。こういうとき、経済学の手法は役に立つ。人々の意思決定、そして行動を分析する学問だからだ。その研究の最先端を、気鋭の経済学者がわかりやすく案内する。
目次
第1章 結婚の経済学
第2章 赤ちゃんの経済学
第3章 育休の経済学
第4章 イクメンの経済学
第5章 保育園の経済学
第6章 離婚の経済学
著者等紹介
山口慎太郎[ヤマグチシンタロウ]
東京大学経済学部・政策評価研究教育センター准教授。1999年慶應義塾大学商学部卒業。2001年同大学大学院商学研究科修士課程修了。2006年アメリカ・ウィスコンシン大学経済学博士(Ph.D)取得。カナダ・マクマスター大学助教授、准教授を経て、2017年より現職。専門は、結婚・出産・子育てなどを経済学的手法で研究する「家族の経済学」と、労働市場を分析する「労働経済学」(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
遥かなる想い
147
2020年新書大賞第5位。 出産や子育てに関する 思い込みを 経済学の観点から 正してくれる本である。 男女の出会いから、結婚・出産と身近な 話題を やさしく書いているので、 読みやすく 面白い。 あくまでも データによる分析だが、一つの視点として 軽く読める 本だった。2020/06/06
mariya926
140
データでの分析なので信憑性があります。結婚、赤ちゃん、育休、イクメン、保育園、離婚について東大の経済学部で教えられている内容を知ることができます。似たもの同士の結婚や浮気をしやすい職場はなるほどと思いました。母乳の場合は感染性胃腸炎とアトピー性湿疹にかかる割合は減っていて、乳幼児突然死症候群の発生率も減少しています。また保育園通いは高学歴の母親の子どもには影響が少なくても、恵まれていない家庭の子どもや母親には大きな貢献になっていて虐待も防いでいるそうです。家庭については興味があるので読めてよかったです。2020/05/20
ゆいまある
87
ファクトフルネスとは違って、データから導き出される驚愕の真実を述べるのではなく、筆者の仮説をデータで裏付けていく手法。なのでエビデンスとしてやや弱いものまで採用されている印象は残る。母乳神話の否定、3歳児神話の否定に始まり、育児休暇を伸ばすよりも保育園を充実させる方が子供の幸せに繋がると説く。父親が育休を取ることで経済的なダメージはあっても、その後も家事育児もやるようになると言えばメリットが大きいだろう。家庭環境が悪い場合は特に保育園の恩恵は大きい。最後に共同親権の導入の提案。これは日本でも実験して欲しい2020/02/12
海月
82
図書館本。経済学の目線での家族について述べた本。新書大賞にノミネートされた本だったため読んでみたものの経済学だから当たり前だが数字が沢山。読み進めていくうちに新書というよりも論文に思えてきて症状苦痛にも…。ただ海外のデータではあるがイクメンの話ではなかなか興味深く読ませてもらいました!日本も男性に限って育休はもっと少なくしても良いから給料をほぼ満額で数ヶ月にしたらもう少し取りやすくなるんじゃないかなと…。流石に一年は会社から離れるとやっぱり立場が怖くなるもんねぇ。2021/11/24
Nobu A
56
サントリー学芸賞一覧から選んだ一冊。19年初版、翌年第6版。先日読了の同賞受賞作品、小島庸平著書「サラ金の歴史ー消費者金融と日本社会」程ではないが、面白い内容。「三つ子の魂百まで」と言われるように、3歳までの教育が大切なのか。そのような根拠のないものを経済学で分析。結婚、出産、育休、イクメン、保育園、離婚をテーマにした6章立て。マッチングサイトの隠れた有益データ、帝王切開の利点・欠点、他国の育休制度の普及の変遷、離婚データの誤謬等、興味深いトピック目白押し。問題はこのようなデータが政策に反映しているのか。2022/09/29
-

- 電子書籍
- 恋のゴールドメダル~僕が恋したキム・ボ…