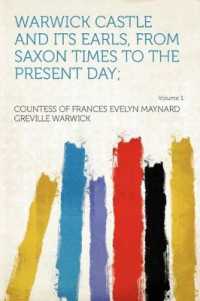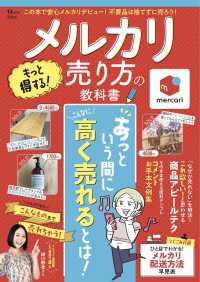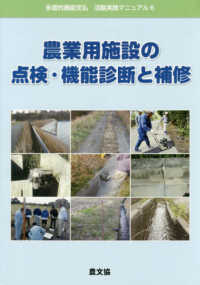出版社内容情報
佐藤優[サトウ マサル]
内容説明
トランプの勝利は、労働者階級の勝利か?世界を覆う格差・貧困。新自由主義=資本主義が生み出す必然に、どう対峙するか?キリスト教神学的アプローチで、廣松渉『エンゲルス論』を読み直す。
目次
同志社大学神学部時代の廣松渉との出会い
カルバン主義者としての青年エンゲルス
シュライエルマッハー神学がエンゲルスに与えた意味
神の疎外
神の収縮と悪の起源
救済の根拠としての民族への受肉
資本家としてのエンゲルス
神的人間の発見
共産主義へ
マルクスの疎外論との対決
弁証法の唯物論的転倒
フォイエルバッハの超克
著者等紹介
佐藤優[サトウマサル]
1960年東京都生まれ。’85年に同志社大学大学院神学研究科修了後、外務省入省。在英国日本国大使館、在ロシア連邦日本国大使館に勤務した後、本省国際情報局分析第一課において、主任分析官として対ロシア外交の最前線で活躍。2002年、背任と偽計業務妨害容疑で東京地検特捜部に逮捕され、’05年に執行猶予付き有罪判決を受ける。’09年に最高裁で有罪が確定し、外務省を失職。現在は、執筆活動に取り組む。’05年に発表した『国家の罠 外務省のラスプーチンと呼ばれて』(新潮文庫)で第59回毎日出版文化賞特別賞受賞。’06年に『自壊する帝国』(新潮文庫)で第5回新潮ドキュメント賞、第38回大宅壮一ノンフィクション賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
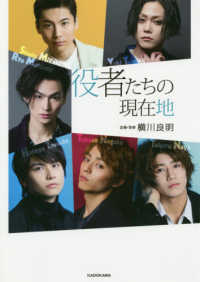
- 和書
- 役者たちの現在地