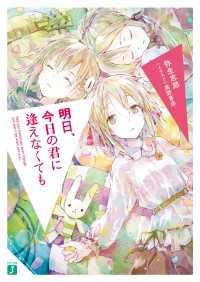出版社内容情報
小川さやか[オガワ サヤカ]
目次
プロローグ Living for Todayの人類学に向けて
第1章 究極のLiving for Todayを探して
第2章 「仕事は仕事」の都市世界―インフォーマル経済のダイナミズム
第3章 「試しにやってみる」が切り拓く経済のダイナミズム
第4章 下からのグローバル化ともう一つの資本主義経済
第5章 コピー商品/偽物商品の生産と消費にみるLiving for Today
第6章 “借り”を回すしくみと海賊的システム
エピローグ Living for Todayと人類社会の新たな可能性
著者等紹介
小川さやか[オガワサヤカ]
1978年愛知県生まれ。専門は文化人類学、アフリカ研究。京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科博士課程単位取得退学。博士(地域研究)。日本学術振興会特別研究員、国立民族学博物館研究戦略センター機関研究員、同センター助教を経て、2013年より立命館大学大学院先端総合学術研究科准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 4件/全4件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
rico
122
タンザニアのインフォーマル経済についてのフィールドワークから見えたもの。必要なだけ稼ぐ、人のつながりを頼りに融通無碍に自分の持てるものを生かし、生業を見つけて生きていく。組織化された経済システムにどっぷりつかってる私にはとても自由に見える。これは本格的な経済成長に至る途上の徒花か、それとも行き詰りつつある資本主義への挑戦状か。最近読んだ「新人世の資本主義」で提示されている解、「脱成長コミュニズム」と重なるような気もするが、時間も経ってる。スマホ決済的なもののその後、中国の影響力。今どうなってる?続報期待。2021/10/22
けんとまん1007
93
その日暮らしの言葉からくるものと、随分違った印象を持った。下からのグローバリゼーション。そんな言い方で述べられているが、国境もなんのその、実態経済と実際の生活という視点でものを見ると、こうなるんだというのが興味深い。俗に、先進諸国といわれている国で当たり前と思われていることとは、まったく異なる世界観がある。多くの可能性を探りながら、あるいは、種を持ちながらの暮らし。お互いの関係性を、きちんと認識したうえでの商取引など、ある意味、とても人間臭いものを感じた。2017/05/01
どんぐり
89
『チョンキンマンションのボスは知っているーアングラ経済の人類学』より前に出た著者の本。ほぼ同じ内容なので、チョンキンを読んでいれば十分かも。タンザニア人のその日その日のために生きるLiving for todayが紡ぎ出す経済や社会のかたちが、新しい社会の可能性に開けているなんて、日本が沈没しない限りまず訪れることはない。先行き不安だらけで、「先がどうなるかわからないことは、新しい希望にあふれている」なんて考えをもつに至ることもない。へえー、そんな世界があるんだなあ、と読んだ。2024/02/06
アナーキー靴下
74
資本主義システムから外れたインフォーマル経済、即ちその日暮らしに焦点を当てることで、資本主義についてのより深い理解を促してくれる本。資本家と労働者という経済構造ではなく、時間の商品化というもう一つの本質について考えさせられる。「未来のために現在を手段化したり、犠牲にする」はまさにで、資本主義の中で生きることは一生未決済の評価損益をよすがに一日一日を売り払うようなものだ。若者は刹那的だとかよく言われるが、システムに組み込まれ、コントロール可能な存在になることへの抵抗感故なのだろう。悲しいかな今の私にはない。2021/06/25
ニッポニア
65
インフォーマルを考察する人類学のおおらかな視点よ。どこでもうたた寝を。以下メモ。1日1日を生き抜くために必要なのは直接体験に基づく自身の力だけ。旅人をもてなすために、生産した食料の40%を分け与える貧しい集落、その幸福度よ。事業のアイデアは捨てられることなく維持され、偶然に積み重ねた経験や人間関係、その時の状況に応じて柔軟に変更されつつ、実現する。前へ前への行き方は、危機に直面した不透明な世界で自らを見失っている状態を意味しない。質の良い商品だけが正義でない、日常使いとしてそこそこのものを安く買う正義を。2024/03/08