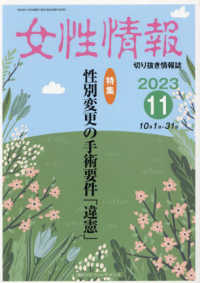内容説明
日本の農業の「現在」を、島耕作とともに楽しく学べる一冊。
目次
第1章 新浪剛史×弘兼憲史の農業立国宣言―いまなぜ農業なのか?
第2章 農業こそメイド・イン・ジャパンを!―大分の“聖域なき”現場を歩く
第3章 日本の農地はおかしなことだらけ―“新しい農地改革”と“農家のサラリーマン化”が必要だ
第4章 合理的農業国オランダに学べ―小さいのに、なぜ世界で勝てるのか?
第5章 誰が「米」を殺すのか―日本の農業を弱くした「補助金」と「農協」
第6章 攻めの農業が日本を元気にする―「獺祭」「近大マグロ」激戦記
第7章 久松達央×弘兼憲史の農業未来論―“大規模農業”と“小さくて強い農業”の共存する国へ
著者等紹介
弘兼憲史[ヒロカネケンシ]
漫画家。1947年、山口県に生まれる。早稲田大学法学部卒業。松下電器産業に勤務後、漫画家として独立(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
pure-oneの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Aya Murakami
80
図書館本。 へええ…。会長島耕作(未読)は農業がテーマなのか。ワタミファームとかローソンが農業に乗り出したというのははじめて聞きました。 オランダはインドネシアでの悪行を聞いていたので嫌いなイメージでしたが合理性という一面を見てちょっとだけ好感がもてました。そして農業大国でありながら輸出特化で自給率にこだわらないとか…?2023/02/25
saga
27
2016年度最初の読了。何が驚いたって島耕作が会長になっていたこと! それは兎も角、日本農業の問題点はやはり第三者が評価することによって明瞭になる。政治家や政府の誤った指針、補助金は、農家の競争力を奪う結果になっている。戦後の農地開放も、農地が細切れになった要因として挙げているが、所有権は素より賃借権ですらままならない現行法制を変えるのは大変だ。著者は農業への一般企業参入を推進する考えのようだが、それが順当であるかどうかは本書では判断できない。2016/04/02
JUN
17
農業改革が必要だと感じた。2023/01/25
8-nosu
16
この本を読むまで農業は「大変・儲からない・泥臭い」あまりいいイメージはなかった。しかし、大分やオランダで実践される先進的かつ合理的な農業経営。日本酒『獺祭』や近大マグロなどの“攻める”農業。これからは「農業こそが日本の次の産業になる」農業が持つ可能性はもの凄く大きいという。農協や補助金、米価のカラクリといった農業に係る諸問題も論じられており、自分のように、農業は詳しくないが「いずれは農業関係の仕事がしたい!」という人向けの農業入門書となっている。強いて言えばTPPにもう少し深く切り込んだ展開が欲しかった。2016/11/26
こういち
16
日本の農業の現状と将来を考える。本書の中ではオランダが比較対象として取り上げられているが、こと農業に限っては完全なる〝井の中の蛙〟だ。学ぶことの根本が置き去りにされた中で、企業経営を枠組みとした農業生産法人が産業育成の救世主となり得るのか。先ずは日本政策金融公庫の審査能力を高めることが必要ではないか。国土の12.2%にあたる農地を、農業従事者のみならず消費者たる一人ひとりが、自らの問題として突き詰める分水嶺はもう目の前にある。2015/11/08
-

- 和書
- 花の曙