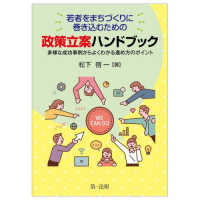内容説明
「教え方を知らない教員」が8割。鈍感教員、学ばない教員、学べない教員、コミュニケーション不全教員、理念欠如型教員―「残念な教員」を量産する学校教育現場の「失敗のしくみ」を踏まえ、過去の教育実践の蓄積と著者自身の取り組みをベースに、未熟練教員と生徒を共に成長させる方法を提示する。
目次
第1章 教育現場の実状
第2章 教師の技術
第3章 教育現場における「評価」
第4章 教員の成長
第5章 授業について
第6章 教員が技術を身に付ける順序
第7章 身に付けてほしい3つの力
著者等紹介
林純次[ハヤシジュンジ]
1975年埼玉県生まれ。京都大学大学院教育学研究科修了。大学卒業後、大手新聞社に記者として入社。事件・事故、医療、政治、教育、高校野球などを担当する。フリーランスジャーナリストに転身した後は、事件や政治の記事を書きながら、カンボジアやパレスチナなどの貧困地帯や紛争地域を取材。一方でサッカー日本代表についても取材執筆を行った。2003年、教育者に転身。2012年度読売教育賞優秀賞(国語教育部門)受賞。現在は関西の中高一貫校で教鞭を握っている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。