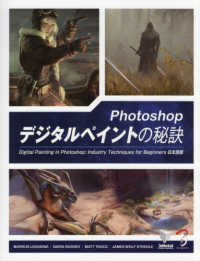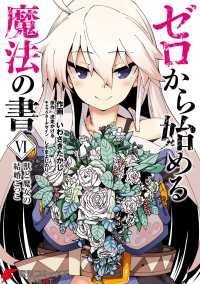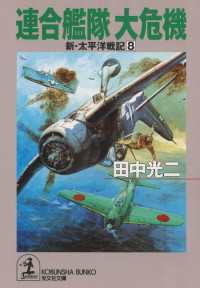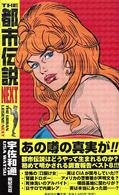内容説明
本書は、やきとりに関する初めての総合的な研究書かつガイドである。「歴史学」「文化学」「老舗学」「社会学」「名店学」「ご当地学」「こだわり学」「調理科学」「肉用鶏学」など、さまざまな切り口でやきとりの謎に迫るとともに、屋台からミシュラン星付きまで、全70軒の店を紹介する。
目次
第1章 やきとりの歴史学
第2章 明治の鶏食文化学
第3章 昭和のやきとり老舗学
第4章 やきとり社会学
第5章 やきとり名店学
第6章 やきとりご当地学
第7章 やきとりこだわり学
第8章 やきとり調理科学
第9章 肉用鶏学
著者等紹介
土田美登世[ツチダミトセ]
1966年生まれ。広島大学卒、お茶の水女子大学大学院(調理科学)修了。「専門料理」「料理王国」編集部を経てフリーランスの食記者、編集者に(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ehirano1
90
新書でこのような内容が読めるとは驚きで、著者が大学の栄養学の教官というのが興味深いです。著者は公務と称して(=実際、公務なんでしょうけどwww)数多の焼き鳥屋を吉田類の酒場放浪記のように訪れたに違いないと勝手に羨ましがっている私がいます。ということで、本書の感想のことはすっかり失念していますwww2025/03/28
akihiko810/アカウント移行中
29
やきとりの歴史からお店の紹介まで、やきとりの入門書であり、専門書。印象度B+ 明治からあった焼き鳥屋の歴史。鶏肉は「卵を産ませてから殺す」ため出回らず高価で、安価になるのは「ブロイラー」が普及する60年代からとか。 名店も詳しく取材しており、チェーン店の「鳥貴族」(とりき)物語も載っている。私は「とりき」に行ったくらいしか知らないので(なかなか旨かった)、ここは興味深く読んだ。 あと、東京で「やきとり」というと、焼きとん・もつ焼きを含むそうだ。 絶対に、焼き鳥が食べたくなる本だ。2025/10/24
たかしくん。
29
焼き鳥を歴史を掘り下げて考察し、ウンチク本にしては秀作だと思います。特に江戸時代末期の鶏肉消費ムーブメントが始まり、戦後のブロイラー、地鶏ブームなどを解説し、今現在やきとり業界の部分も丁寧に抑えてます。今回の収穫は、「つくねを見ると、その店の実力がわかります。」誰の言葉でもないらしいですが、自分のメルクマールに活用したいです。2014/12/21
タルシル📖ヨムノスキー
26
やきとりといえばオヤジの代名詞みたいな印象だったけれど、最近はそうでもないらしい。なにせ「ワインと合うやきとり」とか、「やきとりのコース料理」なんてものまであるらしいので。庶民の食べ物であるやきとりの歴史や社会的位置付け、調理法や鶏肉へのこだわりなど様々な方向からやきとりを解説したのがこの本。やきとりの解説以外にもやきとりの名店を紹介するグルメ本的な役割を果たしている。読みながらここまでくると単なる「酒のアテ」には止まらない奥深い料理なのだと、読んでいて考えを新たにしました。ちなみにあなたはタレ派、塩派?2024/06/21
シルク
16
これを読んで「〇貴族」という焼き鳥屋さんに興味を持った。「280円均一」(当時)と書いてある店をあちこちで見ていたけど、入ったことは無かった。この本にどう、何が書いてあったのかは忘れたのだけど(爆)、とにかく「鳥〇族行ってみよう」って気になったのよな~。行ってみまして、アレコレ焼き鳥、チャンジャ(魚の内臓の……コチュジャン漬け? ムニュムニュ美味しかった)、山芋すりおとしたん焼いたんとか。美味しかったけどさ……焼き鳥、ちっさいなー(笑)! 小さいからひからびたようになって出てくるヨ、と思ったすね。ハハハ。2017/02/20