内容説明
極めて近代的な存在である商店街は、どういう理由で発明され、そして、繁栄し、衰退したのか?よく言われるように、郊外型ショッピングモールの乱立だけが、商店街衰退の原因なのか?さらに、地域コミュニティの要となる商店街の再生には、どういう政策が必要なのか?膨大な資料をもとに解き明かす、気鋭の社会学者による画期的な論考。
目次
序章 商店街の可能性
第1章 「両翼の安定」と商店街
第2章 商店街の胎動期(一九二〇~一九四五)―「商店街」という理念の成立
第3章 商店街の安定期(一九四六~一九七三)―「両翼の安定」の成立
第4章 商店街の崩壊期(一九七四~)―「両翼の安定」の奈落
第5章 「両翼の安定」を超えて―商店街の何を引き継げばよいか
著者等紹介
新雅史[アラタマサフミ]
1973年福岡生まれ。学習院大学非常勤講師。東京大学人文社会系研究科博士課程(社会学)単位取得退学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 3件/全3件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kawa
36
学術的で真面目な内容のこの手の本にメーター登録数937は、上野千鶴子女史のお弟子さんゆえか?商店街に関する真摯な歴史的考察。あまりふれることのない分野で読みはじめは一瞬「しまった」との思いも、中盤以降の日本経済の流れを追いながらの商店街論。思わず耽読と言ってよいだろう。2012年刊で、商店街再生のさわりの処方箋も提示されるのだが、そこから幾年、商店街のシャッター通り化が止まらないところが残念。決して著者の責任ではないのですが…。2024/07/08
1.3manen
32
消費者からすれば、安くて質の良いものを、であるが、商店街は価格で大規模小売店舗に敗北した。規制緩和により、シャッター商店街となった。地域再生と言っていた矢先、3.11となり、復興と再生が軌を一に語られることが多くなった。34ページの零細小売商の保守性というのは納得できる。「これがふつうだ」、「100%じゃないだろ?」とのたまわれる経営者の蛸壺な発言からすればいえることだろう。長が付けば盲腸でも偉いかのような勢いであった。インターネットショッピング、ショッピングモールの台頭で、人柄の悪い人たちに未来はない。2012/11/16
ちくわん
27
2012年5月の本。本書も「社会学」だ。私が東京にいた1975年~90年は、地元商店街がしっかりあった。スーパーもコンビニもあった。商店街を構成する個人商店は住居が店舗を兼ねる。跡継ぎがない場合は廃業かコンビニ。廃業すればシャッターが一つ増える。コンビニにすると近隣の廃業を加速する。こうしてシャッター商店街になる。全部がコンビニになったコンビニ街という所はないのか?そう考えると地元商店街と繁華街の商店街はでは変化が異なるのか。話は変わるが新書はほとんどが「社会学」なのか?2022/02/11
hk
22
これも良著だ。「商店街はいま必要なのか 」と併せて読むことで流通に関する造詣が深まること請け合い。両書籍とも流通業の変遷を掘り下げているが、アプローチの仕方が微妙に異なるため複眼的に流通小売りを捉えられるようになるはずだ。本書では昭和恐慌と敗戦という2つの大分岐において、農村から都市部に流入した人々が労働者と自営業者という「両翼」にわかれたことに着目している。労働者は当然リベラル政党を、多数派だった農民と自営業者が規制をもとめて保守政党を支持したことで55年体制が始動した。だが労働者層が多数派になると…2018/10/25
魚京童!
22
今「金もないけど、就職もしたくな」という若者たちはいったいどのような道を歩んでいるのだろうか?2014/08/12
-
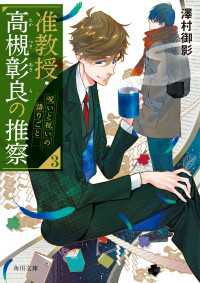
- 電子書籍
- 准教授・高槻彰良の推察3 呪いと祝いの…
-
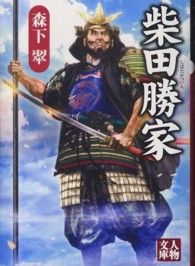
- 和書
- 柴田勝家 人物文庫







