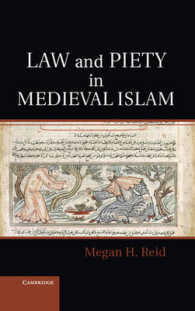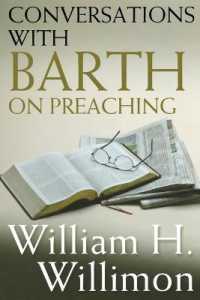内容説明
「つながり」を制す者、組織を制す。ビジネス、感染症、犯罪捜査…多様な分野で応用される最新研究の「怖さ」と「魅力」。
目次
はじめに―ネットワークの怖さと魅力
第1章 対ゲリラ戦略と米軍マニュアル
第2章 電子メールから浮かび上がる業務遂行ネットワーク
第3章 SNSの人脈連鎖
第4章 広告作品「カレシの元カノの元カレを、知っていますか。」
第5章 知人の連鎖と新型インフルエンザつながり
第6章 弱い絆の強さと弱さ
終章 “入る”を制する
あとがき―橋を燃やす
著者等紹介
安田雪[ヤスダユキ]
関西大学社会学部教授。1963年東京生まれ。国際基督教大学教養学部卒業。コロンビア大学大学院博士課程修了(Ph.D.)。東京大学ものづくり経営研究センターなどを経て現職。組織や社会集団を中心に、分野横断的にネットワークの構造と影響を考察する「社会ネットワーク分析」に四半世紀、従事。理工系研究者、企業との共同研究も多数。関係構造の解析以上に、見える化した関係の解釈と、その見えざる影響力の解明に力を注ぐ(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Don2
13
インビジブルエッジでネットワーク分析に興味を持ち入門書として読んだ。著者はネットワーク分析を専門とする教授。エッセイスト的で、軽快で少し斜に構えた文章が楽しい。著者曰く、ある人の情報はその人の友人知人関係からかなりの程度推測できるらしい。確かになあと思うと共に、自分の人生で維持してきた•捨ててきた人間関係を考えてしまった。人脈をネットワーク的にみると、複数の"島"間の橋や結束点となる人が重要で、人脈を生かすには直接の知人の先の人脈をある程度把握する必要があると。キャリア戦略にも活かせそう…だが先は長いなあ2024/03/03
shiorist
7
みえないものをみえるものとして語ることができる人はエライ。自分が主体的に何をなすかよりも、他者からの関与によって主体が決定されちゃう、ってゆーラカン的な話になる。ってことで結論は人間関係の「入りを制す」ことが重要だそうで。2010/11/05
ぴーたん
5
コンビニで「缶ビールとおでん」を一緒に買う人は多いが、「ストッキングと殺虫剤」を一緒に買う人は多くはないという。これは膨大なネットワークを分析すると浮き上がってくること。という序文から引き込まれた。社内の電子メールを分析すれば、どんな文面を書く人がパフォーマンスが高く、良好なネットワークを築いているかわかってしまう。ただし倫理的な問題もありどこまで分析をすすめていっていいのか迷うらしいです。付き合いを見れば人がわかる。特に出て行く関係ではなく、入ってくる関係はコントロールできないので良くわかるそうです。2013/07/23
ゆき
3
ネットワークで関連付けるとありとあらゆる学問がそれこそ紐づいてくる。人とのつながりや流行病の広がりまでもあってなかなか興味深い。2013/02/19
satoben
3
人間関係を分析する、その魅力に触れることができる。人間関係は自分の趣味や思想なんかよりずっと大事であり、関係を見れば人となりが分かる、という前提で議論がスタートする。そこで面白かったのが、人間は関係認知能力が低い、ということ。自分が親しいと思っていても相手が思っていない可能性は非常に高いのだ。なるほど、恋愛で失敗することが多いのもこのためだろう。マーケティングがうまくいかないのもこのためだろう。誰とでも仲良くなる力もいいが、この関係認知の力の大事さを知ることができた。2010/10/29