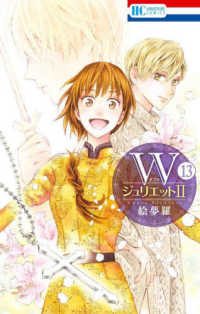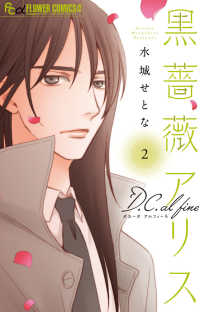内容説明
捕って、屠って、感謝して、頂く。映画『THE COVE』が描かなかった真実。イルカ追い込み漁船に何度も便乗し、「おいちゃん」たちと15年間も交流してきた動物行動学者の“体験的捕鯨論”。
目次
イルカ追い込み漁(沖でのこと;浜でのこと)
太地発、鯨と人の400年史―古式捕鯨末裔譚
イルカを飼うのは「かわいそう」か?
捕鯨業界のこれから
鯨を食べるということ
著者等紹介
関口雄祐[セキグチユウスケ]
1973年千葉県生まれ。千葉商科大学専任講師。1996~2000年、沿岸小型捕鯨担当の水産庁調査員(非常勤)として定期的に太地に滞在。それ以来2003年まで、追い込み漁の経験と行動観察を兼ねて漁船に便乗。その後も、年に1~2度、太地を訪問し交流を続けている。本業は睡眠研究。東京工業大学生命理工学部卒、同大学院博士課程修了、博士(理学)。東京医科歯科大学生体材料工学研究所特別研究員(JSPS特別研究員PD)などを経て2008年より現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 洋書電子書籍
- Would You Rather? H…
-
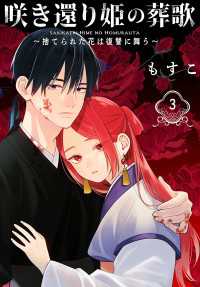
- 電子書籍
- 咲き還り姫の葬歌~捨てられた花は復讐に…