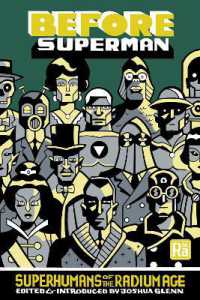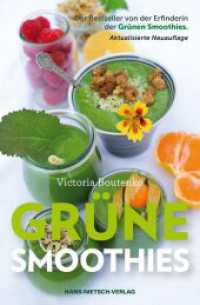出版社内容情報
『想像の共同体』の世界的権威が、現代のナショナリズムの問題から、自身が新たに注目する初期グローバリゼーションの時代までを講義する。アジア、世界を読み解くための新しい視点がある。
内容説明
二四年前、ナショナリズム研究の最重要書のひとつである『想像の共同体』を著したベネディクト・アンダーソン。彼が二〇〇五年、早稲田大学で行った二つの講義を収録するとともに、そのメッセージを丁寧に解説する。世界の見方が変わる、アンダーソンとナショナリズム理論への最適な入門書。
目次
第1部 ベネディクト・アンダーソン講義録(『想像の共同体』を振り返る;アジアの初期ナショナリズムのグローバルな基盤)
第2部 アンダーソン事始(アンダーソン、アンダーソンについて語る;『想像の共同体』再説;グローバリズムの思想史にむけて)
著者等紹介
梅森直之[ウメモリナオユキ]
1962年広島県生まれ。’85年早稲田大学政治経済学部卒、同大学大学院政治学研究科へ進む。91年、シカゴ大学大学院政治学部に留学、Ph.D.取得。早稲田大学政治経済学部助手、専任講師、助教授を経て、同大学政治経済学術院教授。日本政治思想史専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
山口透析鉄
24
図書館本。2005年にWの講演会で話された内容が質疑応答等と共に収録されています。アジア地域の植民地支配を例にした話が多く、米国は唯一アジアを包括的に支配しようとしていた国、といった指摘から始まり、グローバリゼーションは19世紀の電信や国際郵便、や共通語の普及(出版事業の振興)あたりから、と見ているようです。 後半の翻訳者による解説でも、我々は否応なく国家・地域・性別等をこえた新たな繋がりに期待をするべき、とは感じているようでした。地域社会みたいなものは変貌するでしょうが。 これ今だったらどうなりますか。2025/07/09
崩紫サロメ
13
『想像の共同体――ナショナリズムの起源と流行』の著者アンダーソンが早稲田で行った講演とその解説。今やナショナリズム論の古典ともなった『想像の共同体』が書かれた背景を生い立ちから語る。アイルランド人とイギリス人の混血として中国で生まれ、アメリカで育ち、政治学と古典研究を専攻したこと、こうした経歴、特に古典研究がナショナリズム論に大きく影響したという点は非常に興味深い。「他の言語集団に属する人々と感情的なつながりを得る」ことの意義を論じ、「貿易より言語を!」との主張に耳を傾けるべきではないかと改めて思う。2019/11/22
chang_ume
11
2005年講演にて(於早稲田大学)で語られた『想像の共同体』の成果と課題。ナショナリズム研究を認識論的次元に転回させた功績、結果として研究の「文化史」的受容と文芸批評へのインパクト、一方でグローバル化への言及不足などについて本人が語る。その後の研究でアンダーソンが新概念「初期グローバル化」を提唱しながら、出版資本主義の性質を国境に限定されないネーション間の相互交流の促進(接着剤としてのアナーキスト)として再評価し、自説を大きく修正していたことに驚いた。後半の解題(梅森直之)から読むことをお勧めします。2022/07/29
Z
10
『想像の共同体』の背景、反応に対する著者の受け止め、それからの展開を語る講演。『想像』を書いたのは自己の複合的な出自が内的な契機、外的にはベトナム、中国、カンボジアなど社会主義国でのナショナリズムに基づいた戦争が起こったことにある。『想像』ではナショナリズムの契機に出版業と資本主義の結合をあげていたが、翻訳を介した人と思想の伝播を以後強調。『想像』ではアフリカなり南アメリカでの比較的小国による反植民地闘争がおき、西洋への対抗熱がアジアに伝播。イギリスは電信網をアジアまで広げ、インターネットとまでは言わない2018/06/07
ドウ
8
ベネディクト・アンダーソンが早稲田大学で行った講演会の書き起こしと、編者によるアンダーソン概論が収められた小品。『想像の共同体』の翻訳は、ナショナリズムそれ自体を求める方向から増えてきたこと、アナーキストが精力的な翻訳家であったことなど、出版資本主義という魅力的な理論を提示した人らしい、出版・翻訳にまつわる発言が興味深かった。『想像の共同体』に固執も否定もせず、論じきれなかった論点を丹念に紐解こうとする姿勢も好感が持てる。第二部の概論も初学者にはうってつけ。薄くて軽くてサクッと世界の深みを覗ける良書。2019/05/09
-

- 和書
- 文学の遠近法