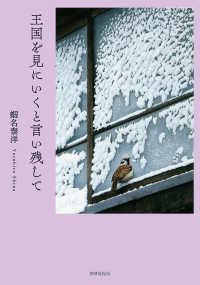内容説明
かつて漢文は、東アジアのエスペラントであり、日本人の教養の大動脈であった。古代からの日本の歴史を「漢字」「漢文」からひもとくことで、日本人が何を思い、どんな試みの果てに、この国が築かれてきたのかが明らかになってくる。日本人にとってまだ漢文が身近だったころ、漢文の力は政治・外交にどのように利用されたのか?彼らは、漢文にどんな知性や思いを込めたのか?―日本の発展の原動力となり、その文化・政治力を支えた「漢文の素養」をもう一度見直し、日本文化の豊かな可能性を提言する。
目次
第1章 卑弥呼は漢字が書けたのか
第2章 日本漢文の誕生
第3章 日本文明ができるまで
第4章 漢文の黄金時代
第5章 中世の漢詩文
第6章 江戸の漢文ブームと近現代
著者等紹介
加藤徹[カトウトオル]
1963年東京都生まれ。東京大学文学部中国語中国文学科卒業、同大学院人文科学研究科博士課程単位取得満期退学。1990~91年、中国政府奨学金高級進修生として北京大学中文系に留学。広島大学総合科学部専任講師を経て、同助教授。専攻、中国文学。『京劇』(中公叢書)で第24回サントリー学芸賞(芸術・文学部門)受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しゅてふぁん
50
日本の歴史と共に漢文の歴史・変遷を追う。時代ごとに漢文の担い手が変わっていく様が興味深い。奈良時代の人々が漢字文化の導入に熱心だったおかげで、漢文訓読法が確立し、現代の私たちも気軽に漢文や漢詩を読むことができるのか。ありがたいことだ。江戸時代に中国国内で禁書になっていた文献が日本で続々と一般向けに売られていたことにはびっくり。私は趣味で漢詩が読めたらいいなと思う程度なので‘漢文の素養’を身に着けようと頑張るわけではないけれど、この本が面白かったので著者の『漢文力』も読んでみよう。2018/11/07
Yamazon2030
21
2021(59)2021/12/25
ひと
19
漢文を読めることが海外(特に中国)の最新情報を速やかに把握できることにつながり、中韓と異なり士大夫階級が不在だったために中間層(町人層)までが漢文を読めたことが日本の国力を支えてきたということが理解できた。明治維新による西洋化の過程で、西洋のことばを日本が漢字に置き換えてきた創造性に驚く。憲法や銀行など、ほとんど発明の域で脱帽。これがあったから、西洋の理解が早まったのは間違いないだろう。その後、漢文軽視となり最近の新語がみんな単なる英語音のカタカナ表記になってしまったのは残念。きんと漢詩も学んでみたい。2025/09/27
樋口佳之
18
漢文授業廃止論がいかに妄言なのかを感じました。実際、大半無味乾燥な受験勉強の中で楽しい授業の一つだったし。/仕事との絡みで、漢文漢字文化圏がギクシャクしない関係ならOSのあり方だってもっと主張できる事があっただろうにと思うこと多いです。/今日の中国で、パソコンやインターネット関連の用語をどんどん「新漢語」に置き換え、自国民にわかりやすいものにしている様子を見ると、まるで明治期の日本のような勢いを感じる。2017/04/27
しょうゆ
11
漢文が日本の文化に与えた影響がわかって面白かった。僧侶階級が呉音に固執したとか平安時代は漢字だけで書かれた文章の方がかっこいいとされていたとか。江戸時代の漢文ブームは何となく知っていたが、思っていたよりも大ブームだった。漢詩文を自在に書けるってかっこいい。日本で戦後急速に漢文の教養レベルが低下してしまったのは仕方ないが、せっかく漢字を使って生活しているのだからもう少し素養があってもいいのではないかと思う。玉音放送が漢文訓読調で国民に伝わりにくかったという話は興味深い。2021/12/12
-
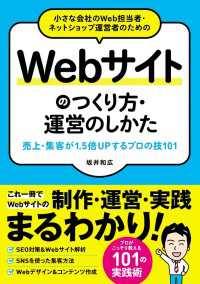
- 電子書籍
- 小さな会社のWeb担当者・ネットショッ…