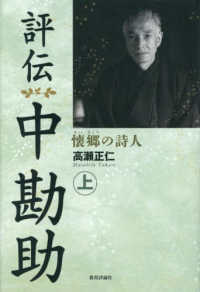内容説明
次第に都市化しつつあった十八世紀なかばのヨーロッパでは、動物への残虐行為がいたるところで見られていた。なかでも、パリの印刷工場で起きた事件は異様だった。そこに勤める職人たちが、猫を一匹残らず集めてきて、皆殺しにするという事件が起こったのだ。しかも猫に対して裁判を行い、厳正なる裁判の結果、有罪判決が下されると猫たちを即席の絞首台に吊す。事件の最大の異様さは、猫を絞首台に吊すと、そこで大爆笑が起きたことである。これらは何を意味しているのか。ホガースの版画とパリの事件から、秘められた謎の答えを探し出す。
目次
第1章 十八世紀、猥雑のロンドン
第2章 コンタは見た―印刷工たちのパリ
第3章 都市の詩学
第4章 この世は笑う
第5章 絞首刑のアーケオロジー
第6章 穀物霊と神話の力
著者等紹介
東ゆみこ[ヒガシユミコ]
1968年千葉県生まれ。お茶の水女子大学文教育学部で人文地理学、学習院大学大学院人文科学研究科博士前期課程で神話学・日本文学を専攻。お茶の水女子大学大学院人間文化研究科比較文化学専攻(博士課程)を単位取得満期退学。現在、学習院女子大学・日本女子大学・都留文科大学の非常勤講師
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
三柴ゆよし
17
漱石もその講義で言及したホガースの絵画と18世紀ヨーロッパにおける猫の虐待虐殺という事例から、古代ギリシア&ゲルマンの神話にまで遡求していく、新書というスタイルにはおよそ似つかわしくない、壮大なパースペクティブをそなえた書物。正直なところ、ほんまかいなと狐につままれたような気分に陥る箇所もある。とはいえ、もと民俗学の徒としては、柳田、折口、熊楠の系譜に連なる、こうした幻視的な射程は、おもしろい人文科学にとっては、どうしたって必要な一要素であると考える。事象の珍奇さに頼り切っているといえばそれまでなのだが。2018/05/06
たまご
16
18世紀ヨーロッパで,現代では動物虐待とみえる事象が繰り広げられていた.それは,なぜ? 2項対立(冨者/貧者,雇用者/被雇用者などなど)だけでは読み解けない,神話につながる古代からのヨーロッパ社会のメンタリティがあった…! と読み解く筆者.「祝祭」は都市化されてお行儀よくなってしまって,そのエネルギーの発露が一つ原因のように思えますが,「吊るす」ことの意味はそこまで肯定的かなとも思いました. クリスマスツリーのオーナメントの起源は死体だ,という(嘘かホントか)話を思い出しつつ.2021/01/30
tom
14
犬を殺す、猫を殺す、ウサギも殺す、おまけに裁判までやっていた。動物裁判というところに反応して、この本を借りてくる。読み始めてしばらくして出てきたのがレヴィ=ストロース、もう少しすると山口昌男ついでギリシャ悲劇やら北欧のオーディンまで登場。大昔読んだよなあと懐かしい気分になる。そして語られるのは祝祭、日常と非日常。近代になって理性優先が言われるようになっても、背景には古代から続く神話の世界がうごめいているというのが結論。でも、この本を読むだけでは、著者の考えの上っ面だけを知るという印象。2021/02/16
きつね
6
ホガースの絵から神話論に遡っていく展開、とても面白い。ただ、最終的に表題の問いへの回答に説得力があるかというと、ちょっと物足りなく思った。もうちょっとホガースの神話教養などを論じてもらうと納得がいくかも。ホガース論をいくつか買ってあるのでもう少し勉強してみます。2017/04/12
コン
3
猫が殺された理由が古代から続く様々な要因(宗教・儀礼・神話など)があることは分かった。 恐らく著者は一つの事象でも、そこには多様な文脈が潜んでおり、多くの解釈ができることを証明したかったのだと思う。 しかし記号論や構造主義などの方法論の説明から、宗教や神話や文化の説明と、詰め込みすぎだし、 また余りに散文すぎて、まとまりに欠けていたというか、それらが直接どれほど主因として働いているかがよく分かりませんでした。 タイトルのインパクトに期待すると、内容は全体的に味気ない結果になると思います。2011/08/29
-

- 洋書
- Voter Z