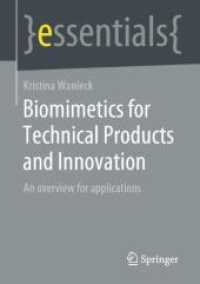内容説明
酒は純米、燗ならなお良し―。本来、米と水だけでつくる日本酒は、これ以上ないほど安全で健康的な食品である。しかし戦中戦後の緊急避難策として始まったアルコール添加が定着し、経済効率のみが優先されてきた結果、「日本酒は悪酔いする、飲むと頭痛がする」といった誤解を生じさせ、今日の危機を迎えた。我が国固有の文化である日本酒はどうあるべきか。六〇年近く、第一線の酒造技術者として酒一筋に生きてきた「酒造界の生き字引」が本当の日本酒の姿と味わい方を伝える。
目次
第1章 日本酒とは純米酒のことである
第2章 純米酒に対する誤解
第3章 純米吟醸酒を燗にして飲む
第4章 米とつくりの重要性
第5章 酵母の命が酒の強さを生む
第6章 誰が日本酒をダメにするのか
第7章 良い酒販店、飲食店の見分け方
第8章 上原流「〓(き)き酒」指南
著者等紹介
上原浩[ウエハラヒロシ]
1924年鳥取県生まれ。広島財務局鑑定部を経て、鳥取県工業試験場に勤務。定年退職後も、酒類審議会委員、鳥取県酒造組合連合会技術顧問、「蔵元交流会」常任顧問、日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会(SSI)最高技術顧問などを兼任。酒造技術指導の第一人者で、酒造界の生き字引的存在。三倍増醸全盛の時代から純米酒の復活に尽力してきた。漫画『夏子の酒』に登場する「上田久先生」の実在モデルとしても有名
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
藤井宏
12
ワインやビールの製造と違い、日本酒は糖化と発酵の過程が同時に進行する世界に類を見ない高度な醸造酒。一千数百年の歴史の中で培われてきた伝統文化。アルコールの添加をやめ(純米酒)、アルコール度数をワイン程度に下げれば、国際的にもっと評価されるだろうと。精米歩合を上げると酒作りの難易度があがる。純米大吟醸という名前だけでありがたがっていたのは反省。とても奥が深い。「古い川柳に曰く。酒も煙草も女もやめて、百まで生きたバカがいる。私は真っ平ご免である。」の締めくくりに笑った。2024/12/07
双海(ふたみ)
12
「酒は純米、燗ならなお良し」…米が余って困る時代に、なぜアルコール添加の酒が8割以上を占めているのか。消費量が落ちる中でなぜ回転率ばかり考えて熟成を省略するのか。名ばかりの山田錦で作った名ばかりの純米酒。酒造家にも消費者にも落ち度がある。私も消費者の一人として"本物"を飲みたいと思う。2018/12/31
おおた
7
経験に裏打ちされた日本酒業界への強烈なアジテーション。なるほど、「上原派」なる人々が存在するのもうなづける、清酒ではない日本酒を追求する著者の背中を拝むことができる入門書。そして毎年同じ味の酒ができるわけではないことや、本来はワインのようにある程度熟成してから飲むものだ、など、骨太の常識を叩きこまれます。本書が出てから10年、日本酒業界はどのように変わったのかは、自身の舌で感じるしかない。2014/03/28
OjohmbonX
6
高度なベテラン技術者による業界批判は、めちゃくちゃ面白い。技術的な話と、業界構造と、歴史的な経緯とが、ものすごく具体的に語られるので、読んでてエキサイティングだった。著者の方向性は明確で、日本酒がワインのように世界的に評価されて生き残るには、面倒でもごまかしがない作り方をせざるを得ない、戦後の米不足時代の対応や経済効率優先の対応を続けていると埋没するからダメだ、という話だと思う。個人的には体質的にアルコールをほぼ全く飲めないので、読んでも実際に楽しめないのが悲しいけど、とにかく面白かった。2023/07/22
LaVieHeart
5
私の周りには、「日本酒は悪酔いする」「日本酒は二日酔いになる」という人が多いので、身近な所から誤解を解けるように日本酒の知識を深めたいと思って手に取った1冊。 「酒は純米に限る!」と思っていたが、何だか自分の舌を肯定してもらえたようでとても嬉しい(笑)2021/05/29