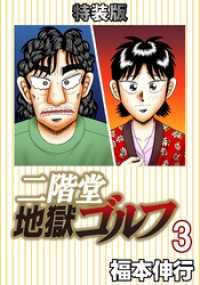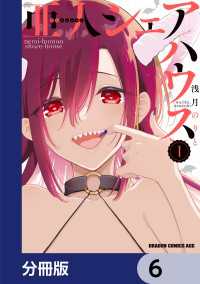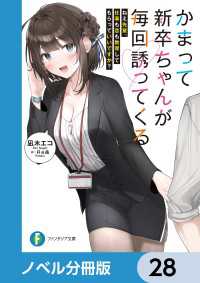内容説明
幼い頃から蒸気機関車に憧れていた少年が国鉄に入ったのは、戦時中の昭和18年、14歳だった。名古屋機関区の一員となり、機関車掃除をする庫内手に。全身が真っ黒になる辛い機関車磨きの日々を乗り越え、鉄道教習所での厳しい訓練を終えると、晴れて機関助士に。やがて、花形の東海道本線に乗務する。機関士と機関助士の固い絆、空襲の中での命がけの乗務と仲間の殉職。終戦の日、敗戦のショックで茫然自失の中、機関士に励まされていつも通り機関車を走らせた…。機関車乗務員の青春の記録。
目次
第1章 蒸気機関車に憧れて国鉄へ(蒸気機関車ファンの少年;福井機関区 ほか)
第2章 汗と涙の“カマ焚き”修業(鉄道教習所機関助士科;浜松工場見学と修学旅行 ほか)
第3章 戦火をくぐり抜けた少年機関助士(機関区での入換えとB6;カンテラとシリンダオイル ほか)
第4章 あの日も汽車を動かした(空襲、機銃掃射;戦況の悪化で機関車を疎開 ほか)
著者等紹介
川端新二[カワバタシンジ]
昭和4年(1929)1月、福井県福井市生まれ。昭和18年3月国民学校高等科卒業。18年4月国鉄に就職し、名古屋機関区庫内手となる。19年6月機関助士となり、関西本線や東海道本線の蒸気機関車に乗務。28年からは電気機関車で機関助士を務めた後、32年7月蒸気機関車に戻り、機関士に。名古屋地区最後の蒸気機関車に乗務。その後は電気機関士として、東海道線のブルートレインなどに乗務。指導機関士として3年間、後進の指導をした後、59年3月退職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Degawa
rbyawa
えふのらん