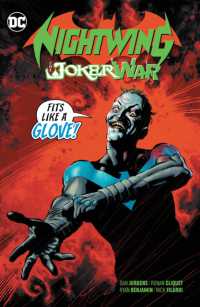内容説明
一度火を落とした蒸気機関車を再び走らせる状態に戻す「動態保存」。その復活はニュースになり、観光の目玉となる。だがそこには「マニア趣味」「郷愁」「客寄せパンダ」的動機だけでは決してなし得ない、数多くの男たちの崇高な使命感と仕事人生を懸けた奮闘があった。動態保存を成し遂げ今も格闘中の大井川・秩父・真岡の3社と、中核的存在の国鉄~JRの事例から、その歴史と現状、今後の課題を、かかわった人々の熱い思いを織り込みつつ検証する。
目次
序章 水と油の塊
第1章 保存鉄道への道
第2章 煙がつなぐ地域の輪
第3章 三セクに開く少年の夢
第4章 人類の偉大な産業遺産
第5章 「金」と「技術」の壁
終章 残すのが義務
著者等紹介
青田孝[アオタタカシ]
1947年東京生まれ。日本大学生産工学部機械工学科で鉄道車両工学を学ぶ。卒業研究として1年間、旧国鉄の鉄道技術研究所に通う。70年、毎日新聞社入社。成田支局で航空機関連部門を取材。以後、メディア関連を担当する編集委員などを歴任後、03年退社。フリーランスとして執筆活動を続けている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
rbyawa
0
e034、現在大井川鉄道と(ダムと鉄道の本でも出てきてたね)、秩父鉄道、真岡鉄道で定期運行? してる蒸気機関車の本で、大井川鉄道が3年くらいで飽きられるんじゃないのかなぁ、と心配していた危惧だけは問題なく、今も地域そのものに人を引き付ける役はこなしているものの、だがそもそも寿命があるものを引き伸ばしている関係で非常にコストが掛かり、その技術も失われている中で一体どこまで、どのように守っていくのかジレンマも多く。ただ、大井川鉄道が「SLを保存するために存在している」とまで言われるとそれはそれでって思うかなw2014/02/03
Guro326
0
蒸気機関車が姿を消したのは自分が生まれた頃。なので現役ではなく全てこの動態保存しか見たことがない。だがしかし、140年の鉄道の歴史の初まりはイコール蒸気機関車であり、それは人類が初めて手に入れた大型動力機械にほかならない。今でこそ産業遺産という言葉があるが、動かすからこそ伝承される技術もある。スコップからボイラーまで。/梅小路とやまぐち号の経緯は昔過ぎてよく知らなかった。簡潔にまとめられている。/ATSでは速度計が電気式でないと。延命治療と同種同様の保存がいつまで続けられるか。2012/10/09