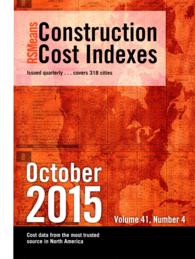内容説明
長年にわたって日本の鉄道経営の中枢にいて、それぞれの時代の舵取りをしてきた著者が、環境問題、エネルギー問題などで鉄道に対する新たな期待が高まっている現在、今後のあるべき鉄道の展開を視野に入れながら、あらためて振り返った昭和の鉄道史。明治・大正の前史から、戦前の興隆期、戦時下、戦後復興期、高度経済成長期、昭和40年代以降の転換期までの、それぞれの時代の鉄道の実像を多彩な資料とともに解説する。
目次
前史1 明治期―鉄道の創業と発展
前史2 大正期―鉄道の拡充期
昭和の鉄道1 昭和元年~15年―興隆期の鉄道
昭和の鉄道2 昭和16年~20年―戦時下の鉄道
昭和の鉄道3 昭和20年代―戦後復興期の鉄道
昭和の鉄道4 昭和30年代―高度経済成長の鉄道
昭和の鉄道5 昭和40年代以降―転換期の鉄道
著者等紹介
須田寛[スダヒロシ]
昭和6年生まれ。29年3月京都大学法学部卒。同年4月日本国有鉄道入社、昭和62年4月東海旅客鉄道(株)代表取締役社長、平成7年6月同社代表取締役会長、16年6月同相談役(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。