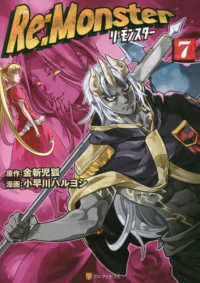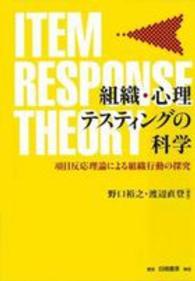出版社内容情報
ベテラン通訳者が、通訳技術のすべてを公開。
長年の通訳者・通訳養成者としての経験をもとに、通訳者の訓練法および通訳者になるための勉強法を具体的に提示。
CDには、実際の国際会議、セミナー、講演会、対談などからとった “authentic”な素材を収録。さらに、著者のモデル通訳も収録。
通訳技術を学びたい人にも、通訳技術や理論を教える人にも役立つ。
著者紹介/著者による他の著作等
小松達也(こまつ たつや)
明海大学教授、(株)サイマル・インターナショナル顧問。数多くの政府間、民間の重要会議、交渉、シンポジウム、講演会などの通訳、アポロ計画以来NHKなどでのテレビ通訳など豊富な通訳経験。特に1986から93年まで先進国首脳会議の主席通訳者を務める。
主な著書:『英語で日本を話そう』(サイマル出版会、1986)、『訳せそうで訳せない日本語』(ジャパンタイムス、2000)、『通訳の英語 日本語』(文芸春秋社、2003)。
第1章 通訳の仕事
1.通訳方式による分類
1-1 逐次通訳/1-2 同時通訳/1-3 リレー通訳/1-4 サイト・トランスレーション/1-5 ウィスパー通訳
2.形態による分類
2-1 会議通訳/2-2 ビジネス通訳/2-3 コミュニティー通訳/2-4 放送通訳/2-5 法廷通訳/2-6 手話通訳
第2章 通訳と言語
1.通訳に必要な言語力
1-1 欧米の考え方/1-2 AIIC(国際会議通訳者協会)の規定/1-3 通訳者養成機関
2.わが国の言語事情と通訳者養成
3.話し言葉と書き言葉
4.通訳と翻訳
4-1 知的作業としての通訳と翻訳/4-2 仕事としての通訳と翻訳
第3章 通訳の過程
1.通訳の基礎としての逐次通訳
2.通訳作業の流れ
2-1 理解/2-2 リテンション/2-3 再表現
3.母国語(L1)と外国語(L2)
第4章 理解
1.「センス」を捉える
2.幹と枝葉を分ける
3.知識の役割
4.論理の流れをつかむ
5.イメージ化する
第5章 ノートのとり方
1.記憶
2.ノートテイキングの原則
2-1 理解を優先/2-2 できるだけ簡潔に/2-3 数字と固有名詞
3.メイン・アイディアと論理の流れ
3-1 センテンスとキーワード/3-2 論理の流れを捉える/3-3 レイアウト:縦方向にノートする
4.ノートテイキング上級編
4
6.ウィスパー通訳
第9章 英語学習への適用
1.通訳訓練が英語学習を促進する要因
1-1 興味の持てる教材/1-2 知識の習得につながる/1-3 学習者主体の訓練/1-4 結果や評価がすぐ得られる/1-5 具体的目標があるため学習動機が高い
2.英語力向上のための具体的方法
2-1 リスニング・コンプリヘンション/2-2 シャドウィング/2-3 ノートテイキング/2-4 スピーキング
3.英語学習への適用の限界
第10章 通訳者への道
1.これまでの経緯
2.通訳界の現状
2-1 技術の習得/2-2 エージェンシーとの関係/2-3 仕事の種類/2-4 プロ通訳者のキャリア
3.将来の展望
4.通訳の仕事の魅力
内容説明
長年の通訳者・通訳養成者としての経験をもとに、通訳者の訓練法および通訳者になるための勉強法を具体的に提示。
目次
第1章 通訳の仕事
第2章 通訳と言語
第3章 通訳の過程
第4章 理解
第5章 ノートのとり方
第6章 再表現
第7章 サイト・トランスレーション
第8章 同時通訳
第9章 英語学習への適用
第10章 通訳者への道
著者等紹介
小松達也[コマツタツヤ]
現在、明海大学教授、(株)サイマル・インターナショナル顧問、NPO法人通訳技能向上センター理事長。東京外国語大学英米科卒業。1988~97年、サイマル・インターナショナル社長。通訳歴:1960~62年、日本生産性本部駐米通訳員。1963~66年、米国国務省言語課通訳員。1966年~現在、サイマル・インターナショナル通訳者。数多くの政府間・民間の重要会議、交渉、シンポジウム、講演会の通訳、アポロ計画以来NHKでのテレビ通訳など、豊富な通訳経験を持つ。1979~93年までサミット(主要国首脳会議)の通訳者を務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- CD
- 能登有沙/おやすみ星